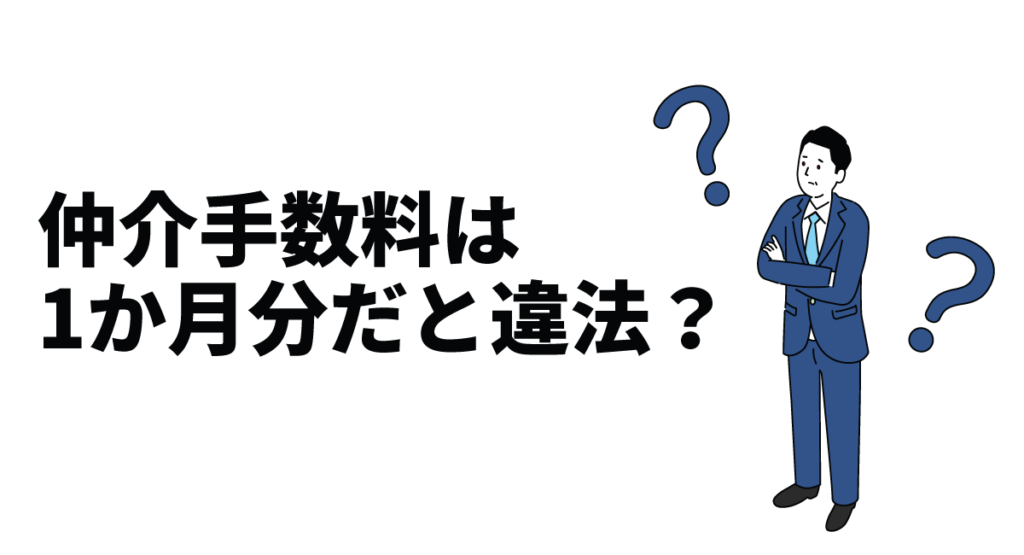
「仲介手数料1か月分は違法」という疑問が、SNSやネット記事などを通じて広がっています。しかし実際には、借主や貸主の承諾を適切に得ていれば、1か月分の手数料を請求することは法律上問題ありません。
そこで今回は、こうした誤解が生まれた背景を整理するとともに、仲介手数料の法令上の上限や実務上の注意点についてわかりやすく解説します。クレームやトラブルを避けるための書面の整備、説明の工夫についても具体的にご紹介します。
仲介手数料とは?

仲介手数料とは、物件の賃貸や売買で、不動産会社が受け取る報酬です。
媒介契約に基づいて発生する正当な費用ですが、金額や請求方法をめぐって誤解が生じやすいものでもあります。とりわけ、手数料の上限や、借主のみに請求・支払いが生じるケースなどは、正しい理解と説明が必要です。
ここでは、仲介手数料の基本的な仕組みや、請求の根拠、発生のタイミングについて整理します。
また、まずは仲介手数料について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
関連記事:賃貸の仲介手数料とは?計算方法や仕訳方法、値引き交渉を断れるケースも解説
仲介手数料の法律上の上限
不動産会社が借主・貸主の双方から受け取れる仲介手数料の上限はそれぞれ、宅地建物取引業法で「賃料の0.55カ月分以内」と定められています。合計で最大1.1カ月分の手数料を受け取ることが可能です。
ただし、借主または貸主のどちらか一方から0.55カ月分を超えて受け取る場合は、その負担者から書面による承諾を得ることが必要です。たとえば、借主から賃料1カ月分を請求する場合は、貸主から手数料を受け取らない旨を明示し、書面による承諾を借主から取得することが求められます。
仲介手数料は誰が支払う?
法令上は、貸主・借主それぞれから最大0.55カ月分を受け取ることが原則ですが、実務では次の3パターンに分かれます。
- 貸主と借主の双方から受け取るケース
- 借主のみから受け取るケース
- 貸主のみから受け取るケース
いずれの場合も、必要な同意があれば宅建業法上の問題はありません。日本では「借主が全額を負担する」という慣習が一般的で、借主に1.1カ月分(賃料1カ月分+消費税)を請求するケースが主流です。
仲介手数料を1カ月分請求しても違法ではない
近年、SNSなどで「仲介手数料の1カ月分請求は違法」といった発信が散見されます。実際には、借主・貸主の承諾を得ていれば、賃料1カ月分の仲介手数料を請求することは法的に問題ありません。
不動産実務においては、この点を正しく説明し、書面での同意取得を確実に行うことがトラブル防止のポイントとなります。また、事前に「最大で賃料の1.1カ月分が発生する可能性がある」と伝えておくことで、顧客の納得感も得やすくなるでしょう。
駐車場の仲介手数料は1カ月分以上かかることもある
ここまでは居住用物件のケースを中心に解説してきましたが、駐車場については事情が異なります。
月極駐車場の賃貸借契約は、宅地建物取引業法の適用対象外であるため、仲介手数料の上限規定は設けられていません。そのため、手数料額は各社で自由に設定することが可能です。賃料1カ月分を超える金額を設定しているケースも見られます。
ただし、成果報酬として収受する性質である以上、金額や内容については事前に説明し、合意を得ておくことの重要性は変わりません。トラブルを防ぐためにも、しっかりと説明し、合意を得ておくことが望ましいです。
仲介手数料1カ月分請求が違法と言われる理由
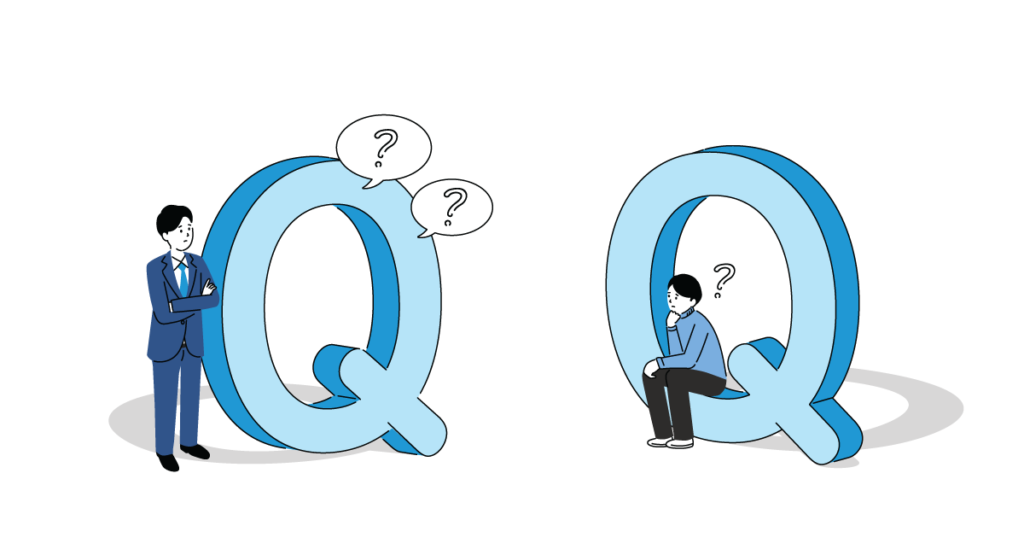
「仲介手数料が1か月分=違法」といった情報が、SNSやブログで拡散されています。その背景には、判例の一部が誤って解釈されていることや、不動産会社による説明不足などがあります。ここでは、誤解が広まった経緯について整理します。
SNSやブログなどでの誤情報の拡散
個人のSNSやブログでは、「仲介手数料が1か月分=違法」といった誤った情報が発信されているケースが散見されます。宅地建物取引業法への理解が不十分なまま、情報を発信されるケースが少なくないようです。
こうした誤解が広がった要因の一つに、2020年1月の東京高等裁判所の判決があります。この判決では、借主の承諾を得ないまま、賃料1か月分の仲介手数料を請求したことが問題とされました。媒介契約が成立する前に、手数料に関する明確な合意がなかった点が、違法と判断された理由です。
一方で、この判決は「承諾がなければ請求できない」という従来の法解釈を確認したものにすぎません。「1か月分の請求が常に違法」というわけではないことも押さえておく必要があります。
正確性を欠く不動産会社の説明
借主に仲介手数料を請求する際は、いくつかの基本的な情報を明確に伝える必要があります。たとえば、貸主からも手数料を受け取っているか、表示が税込か税別か、などです。こうした点を十分に説明しないまま仲介手数料を請求すると、借主の納得が得られず、トラブルにつながる可能性が高まります。
借主が手数料を全額負担する場合は、事前に明確な承諾を得ることが求められます。しかし実際には、「初期費用明細に1か月分と記載し、署名があれば承諾になる」と考え、明確な承諾を得ないまま処理しているケースも少なくありません。
このような形式的な対応では、借主が契約内容を十分に理解しないまま同意してしまうことにもなりかねません。その結果、「知らないうちに1か月分を請求された」と感じさせ、「違法な請求ではないか」と疑念を持たれることになってしまうのです。
法律で決められた上限額に違反するとどうなる?
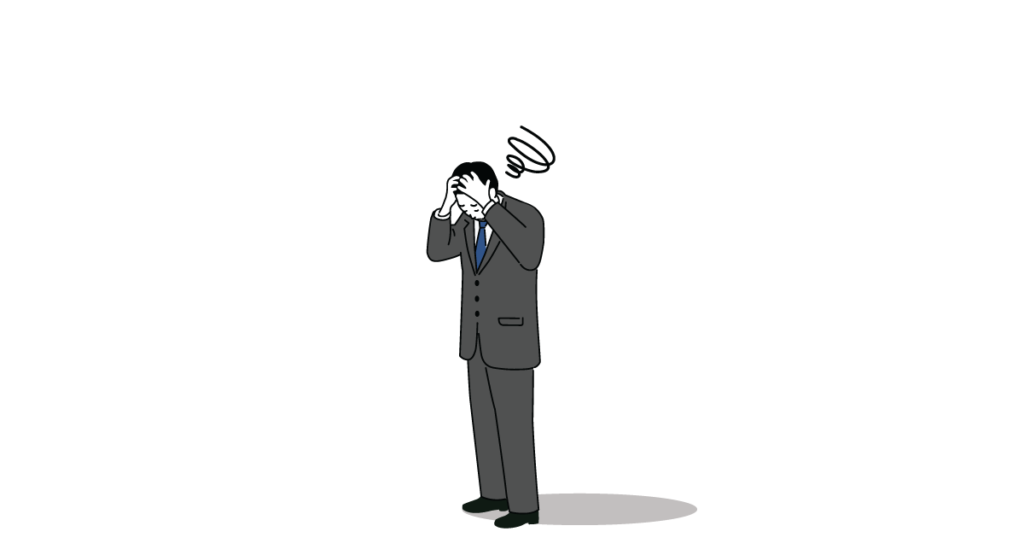
仲介手数料が法律で定められた上限を超えた場合、宅地建物取引業法に基づき罰則の対象となる可能性があります。なお、借主や貸主がそのことを承諾していても、上限超過は許されません。
上限を超過した場合、同法第82条第2号および第80条により、100万円以下の罰金または1年以下の懲役が科される恐れがあります。故意や過失を問わず処分の対象となるため、実務では細心の注意が必要です。
不動産実務で注意すべきポイント
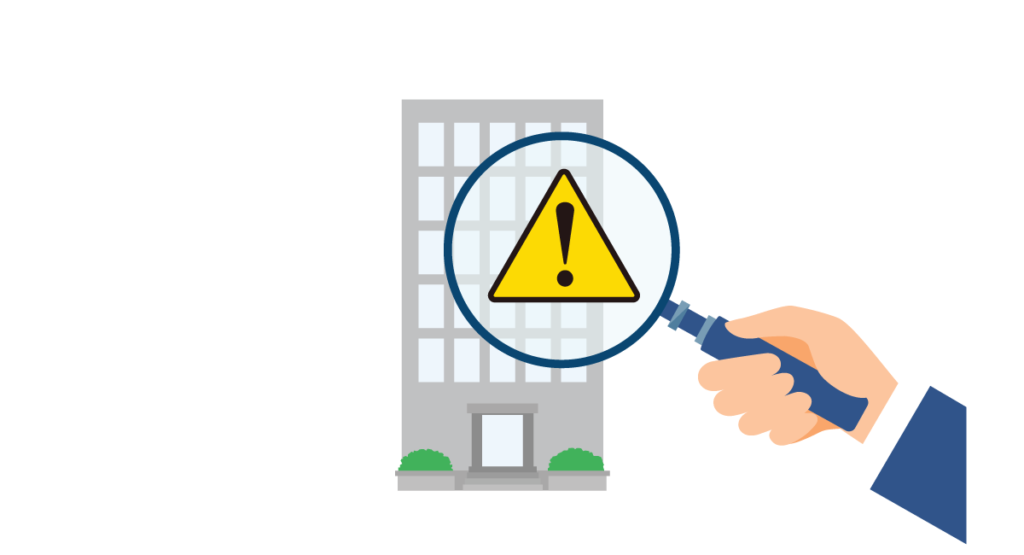
仲介手数料をめぐる誤解やトラブルを防ぐためには、法令への理解だけでなく、日々の業務における対応の正確さが欠かせません。書類の整合性、説明の丁寧さ、社内ルールの徹底など、実務上のチェックポイントを押さえておくことが、クレーム回避と信頼獲得のポイントです。ここでは、実務で押さえておくべき具体的な注意点を整理します。
承諾を書面で取得する
媒介契約書に「報酬として賃料の1カ月分を支払う」と記載され、署名・押印がある場合は、形式上、借主の承諾があったと見なされることが一般的です。
ただし、実務においては署名だけでなく、「本来の上限は0.55カ月分であること」や「1カ月分を請求する理由」を丁寧に説明する必要があります。また、金額や根拠について、明確な意思確認を行うことも重要です。署名があっても、内容を理解しないまま同意しているケースもあるため、トラブルにつながる恐れがあります。
契約書の記載や署名だけに頼らず、説明内容の記録や、負担割合・金額の根拠をしっかりと伝えようとする姿勢が求められます。
手数料額と内訳(税別・税込)を明記する
借主から賃料1カ月分(消費税込1.1カ月分)の仲介手数料を受け取る場合は、書面による承諾が必要です。特に、手数料の金額やその負担理由を具体的に伝えたうえで、内容に納得した承諾であることがわかることが重要です。
承諾書の取得にあたっては、対面契約・郵送・電子署名のいずれでも構いません。ただし、書面の内容に不備があると、後日「説明が不十分だった」と見なされ、承諾が無効と判断される可能性があります。
こうしたリスクを避けるためにも、書類は内容の整合性に注意して作成・保管する必要があります。保管期間に法的な決まりはありませんが、契約終了後も最低2年間は保存しておくことが推奨されます。顧客対応や行政対応での証拠として活用できるよう、社内ルールを定めておくと安心です。
なお、承諾内容は媒介契約書・重要事項説明書・承諾書など複数の書面に分散されるのが一般的です。そのため、各書面の記載内容に矛盾がないよう、事前に整合性をチェックする体制を整えておくことが重要です。
以下に、各書面ごとのポイントをまとめます。
■媒介契約書(媒介依頼契約書)
手数料請求の根拠となる書類です。借主・貸主のいずれと契約する場合であっても、報酬額や支払条件を明記します。借主が全額を負担する場合は、借主の承諾がある旨の記載が重要です。
■承諾書(借主からの手数料1カ月分受領同意書)
手数料の金額、税込・税別の表示区分、負担理由(例:「貸主から受領しないため」)などを明記します。口頭説明だけでなく、書面と署名(または電子署名)の形で残すことが必要です。
■重要事項説明書
宅地建物取引士が交付する法定書類です。手数料の負担者や金額、消費税の取り扱いを明記します。承諾書の内容と一致していることが求められます。
■賃貸借契約書
仲介手数料の支払いに関して記載しておくと、後から「説明を受けていない」「聞いていない」といったクレームがあった際に、合意内容を根拠として示すことができます。記載義務はありませんが、内容を明記しておくことが望ましいです。
■案内図面・募集図面・見積書などの営業資料
初期接点となる各種資料にも注意が必要です。税込表示かどうか、誤解を招く表現がないかなどを確認しておきましょう。
「1か月分」請求の理由を説明する
借主に仲介手数料を請求する際は、税込か税別かを明確に区別し、総額で表示する必要があります。たとえば、家賃が8万円の場合は「仲介手数料8.8万円(税込)」のように提示するのが基本です。
消費者庁や全国宅地建物取引業協会連合会も、価格の誤認を防ぐために税込表示を推奨しています。税抜価格だけを表示したり、税込・税別の区別が曖昧だったりすると、「聞いていた額と違う」といったクレームにつながる恐れがあります。
仲介手数料の金額表示は書面だけでなく、対面説明や電話、メールなど、さまざまな接点で一貫して明示することが重要です。表示にばらつきがあると、不動産会社側への信頼感が損なわれることにもなりかねません。
そのためにも、社内で「税込表示ルール」や「説明用フォーマット」を整備しておくと、対応を統一しやすくなります。現場でのばらつきや、ケアレスミスによる誤表示の防止につなげられるでしょう。
重要事項説明書との整合性を確認する
宅地建物取引士が行う重要事項説明では、仲介手数料の負担区分や金額も明示する必要があります。
重要事項説明と、別途取り交わしている承諾書の記載内容にずれがあると、「説明と請求が違う」といったクレームにつながる可能性があります。そのため、それぞれの内容が一致しているかどうかを、事前に必ず確認しておくことが重要です。
これらの確認は、特に繁忙期などには見落とされがちです。また、仲介手数料の情報が複数の書類に分かれて記載されている場合は、情報の更新漏れや記載ミスが起きやすくなります。そのため、社内におけるチェック体制を整えておくことは、リスク回避のポイントの一つと言えるでしょう。
また、重要事項説明書や賃貸借契約書に仲介手数料の内訳を明記しておくと、後日の確認がスムーズになります。顧客との認識のずれを未然に防ぐことができ、「契約書に記載がない」「説明を受けた記憶がない」といったクレームの予防になるでしょう。
重要事項説明書について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
関連記事:不動産取引における重要事項説明書とは?内容や説明方法も解説
顧客への説明を標準化する
担当者ごとに説明内容が異なると、情報の抜け漏れや伝達ミスが発生しやすくなります。そのため、対応内容を記録に残し、説明をテンプレート化・標準化するようにしましょう。誰が対応しても一定の品質で説明できる体制が整えば、顧客満足度や業務の信頼性向上につながります。
説明の標準化には、トークスクリプトや説明用資料の整備が有効です。特に、新人スタッフや不慣れな担当者の場合は、あらかじめ用意された説明内容に沿って対応することができれば、顧客対応のばらつきを防ぎやすくなります。
また、宅建業法や景品表示法などの関連法令に対応するためには、定期的な法令研修も欠かせません。法改正に即応できる体制を整えておけば、法令違反のリスクを抑え、コンプライアンスの維持がしやすくなるでしょう。
その一方で、法改正のたびに契約書や書式を手作業で見直すことは、現場にとって大きな負担となります。不動産業務支援ツールの中には、これらに自動対応する機能を持ったものもありますので、業務効率化の観点からも有効な対策の一つと言えるでしょう。
『いい生活賃貸クラウド One』は、不動産賃貸業務のデジタル化を支援するサービスです。契約書や取引台帳などの書類作成を効率化するだけでなく、法改正に合わせた書式更新にも対応しています。賃貸借契約に関連する業務を、常に最新の法令に準拠した状態で運用することが可能です。
不動産取引を円滑に進めるために、仲介手数料の理解を深めよう

「仲介手数料1か月分は違法」というのは、一部の誤解や説明不足から生まれたものです。実際には、宅建業法の上限を超えず、借主や貸主の承諾を適切に得ていれば、1か月分を請求することに法律上の問題はありません。
一方、顧客への説明において、「書類の整合性が取れていない」「説明が不十分」といったブレがあると、誤解によるトラブルにつながりかねません。こうしたリスクを軽減するためにも、説明内容や必要書類の書式を標準化・自動化する仕組みづくりが重要だと言えるでしょう。
『いい生活賃貸クラウド One』を活用すれば、法改正に応じた書式更新や記録の一元管理が可能です。社内業務の標準化を進めることで、仲介手数料に関する誤解やクレームを未然に防ぎ、安心・安全な不動産取引の実現につなげることができるはずです。
・執筆者

株式会社いい生活 マーケティング本部
マーケティング部
広報部
全国の不動産市場向けイベント、セミナーなどにて多数登壇、皆様のお役に立つ最新情報を発信しております。


