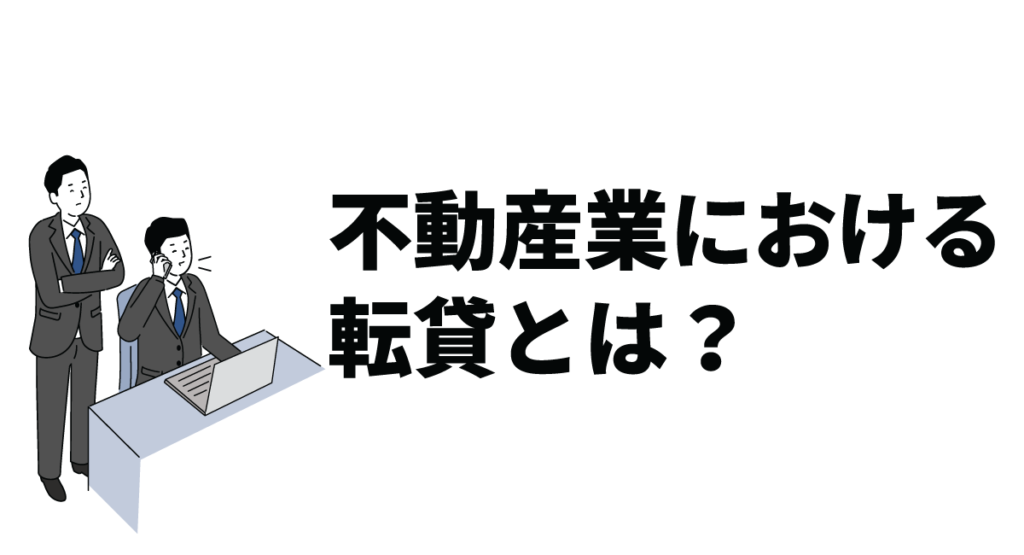
不動産業における転貸(サブリース)は、安定した収益を得るための有力な方法ですが、その一方でリスクも伴います。
転貸(サブリース)を事業として活用するためには、そのメリットとリスクをしっかりと理解し、計画的に進めることが重要です。十分な準備と情報収集が、転貸(サブリース)を成功させるカギといえるでしょう。
そこで今回は、不動産業における転貸のメリットとリスク、そしてサブリースとの違いを整理し、転貸を事業として成功させるためのポイントをわかりやすく解説します。
転貸とサブリースの違い

転貸は、借主がオーナーの許可を得て、物件の契約者としてオーナーと契約を結び、その後、物件を他の人に貸す仕組みを指します。
「サブリースと同じでは?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。転貸とサブリースは、どちらも「借りた物件を第三者に貸し出す」という点では共通しています。ここでは、両者の契約形態や当事者間の関係性について、相違点を解説します。
転貸とは?
転貸は、賃借人(借主)が賃貸人(貸主)の許可を得たうえで、第三者(転借人)に物件を貸し出すことで、「又貸し」とも呼ばれます。賃借人が住んでいる部屋を一時的に別の人に貸し出したり、事業用物件を別の企業に貸すといったケースが該当します。
この場合、賃借人は賃貸人に賃料を支払い、転借人は転貸人(賃借人)に賃料を支払います。物件の利用に関してトラブルが発生した場合は、契約内容にもよりますが、賃借人が賃貸人に対して責任を負うことが一般的です。
サブリースとは?
一方のサブリースは、サブリース会社などが賃貸人から物件を一括で借り上げ、さらにその物件をそれぞれの入居者に貸し出す形態を指します。
その際、オーナーとサブリース会社は、一定期間の賃料保証契約を締結することが一般的です。オーナーは空室の有無に関わらず、契約内容に基づいて、サブリース会社から一定額の賃料を受け取ることができます。物件の管理・維持、入居者の募集・選定、家賃回収などはサブリース会社が行います。
サブリースは転貸の一種ですが、「業者が一括借り上げて管理・運営する仕組み」点で一般的な転貸とは異なります。
サブリース契約については以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
関連記事:不動産管理会社がサブリース契約を結ぶメリット・デメリットとは?オーナーが注意している点も紹介
不動産業における転貸(サブリース)のメリット
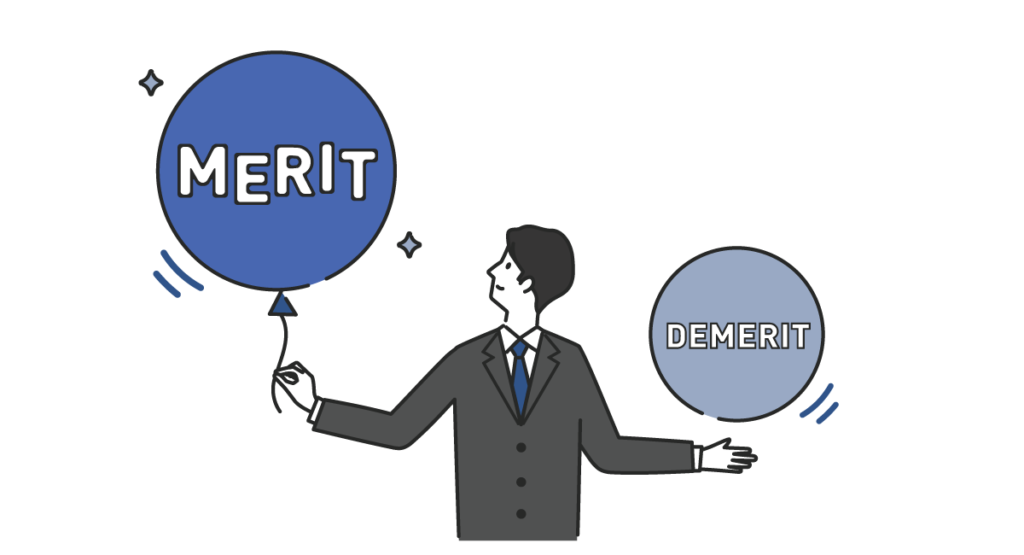
不動産会社にとって、転貸(サブリース)は安定的な収益を得るための有力な手段の一つです。物件の運営管理を一括で引き受けることで、収益の安定化が期待できるほか、幅広い顧客ニーズに対応することで顧客満足度の向上も期待できます。ここでは、不動産会社が転貸(サブリース)を導入することで得られる具体的なメリットについてご紹介します。
収益力の向上
転貸(サブリース)のメリットの一つとして、収益力の向上が挙げられます。不動産会社はオーナー(貸主)に賃料を支払いますが、転借人から得る賃料のほうが高ければ、その差額を会社の利益とすることができます。
このビジネスモデルは、住宅から商業施設、シェアオフィスなどの運営まで幅広く採用されています。特にシェアオフィスは、利用者のニーズに応じた賃料設定や契約形態に柔軟に対応することができるため、不動産会社にとってメリットがあるケースが多いです。市場の需要に応じて賃料を設定できるため、収益の最大化が図りやすいといえます。
差額が多いほど利益も大きくなるため、いかにオーナーから安く借りて転借人に高く貸せるかが収益向上のポイントです。
幅広いニーズへの対応
転貸(サブリース)事業では、特定のニーズに合った物件の提供が可能になります。例えば、企業の社員寮などの住宅ニーズに対応するために、特定の物件を短期的に転貸するといったケースが挙げられます。ニーズに応じて必要な期間だけ効率的に物件を利用したいというニーズと、空室となっていた物件を有効に活用したいというニーズを合致させることが可能です。
これは、居住用物件だけでなく、オフィスなどの事業用物件も同様で、建物一棟ではなくフロア単位で賃借し、転借人に転貸するというケースもあります。
地域や市場のニーズを考慮したうえで、住宅用、商業用、オフィス用などの物件を効率よく管理することで、リスクを分散させることができるでしょう。
ビジネスモデルの強化
一般的に転貸(サブリース)は長期の契約となる可能性が高いため、安定した経営基盤を築きやすいです。
特に店舗やオフィスとして使用する場合は、頻繁な移転のコストや手間を避けることを目的に、契約期間が長期化する傾向があります。そのため、長期契約に基づく安定した収益が確保しやすくなるでしょう。不動産会社は再投資や事業拡大に必要な資金を確保することができ、さらなる規模の拡大を図りやすくなります。
転貸(サブリース)は、ビジネスモデルを強化する重要な手段の一つといえるでしょう。
不動産業における転貸(サブリース)のリスク

一方、転貸(サブリース)にはリスクもあります。
転貸(サブリース)契約を結ぶことで長期的な賃料収入を確保できる反面、予期しないトラブルや費用が発生する可能性があるため、リスク管理が欠かせません。ここでは、不動産会社が転貸事業で直面することが予想される主なリスクについて説明します。
賃料滞納への対応
転貸(サブリース)のリスクとして最も大きいものが、転貸先の賃料滞納です。多くの転貸(サブリース)契約では、転借人が賃料を滞納してもオーナーへの支払いは保証されています。
滞納が長期間続くと、未払いの賃料が積み重なり、回収が難しくなることが一般的です。場合によっては法的措置などが必要になるケースもあります。訴訟となれば、時間とコストがさらにかかり、経営面でのリスクをさらに高めることにもなりかねません。転貸先の滞納が発覚した場合は速やかに対処する必要があります。
原状回復費用の負担
転貸(サブリース)契約には、通常、退去時に物件を元の状態に戻す「原状回復義務」が含まれています。しかし、転貸先の使用によって損傷が生じた場合、その費用を不動産会社が負担しなければならないケースがあります。
特に商業施設やオフィスビルでは、内装や設備の使用頻度が高いため、損傷や破損が起こりやすいです。例えば、壁や床のキズ、配管設備の劣化、照明設備の破損などが考えられますが、これらの修復に高額な費用がかかることがあります。とりわけ、オフィス用の物件では使用者が多いため、通常の使用による損耗を超えた修繕が必要になりがちです。
このように、退去時に発生する原状回復費用が予想以上に大きくなることは少なくありません。なお居住用物件においては、通常使用の範囲であれば、長期間の居住した場合であってもリスクが生じる可能性は比較的低いといえるでしょう。
原状回復については以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
関連記事:原状回復とは?不動産業者やオーナーが知っておくべきガイドラインやトラブル事例も解説
契約違反によるペナルティ
転貸(サブリース)契約では、転貸先が契約内容に対して重大な違反をした場合、オーナーはサブリース会社との契約を解除することがあります。
重大な違反は、契約内容にもよりますが、例えば、長期間の家賃滞納、物件の無断改造、転貸行為、近隣住民への迷惑行為などが挙げられます。
サブリース契約が解除されると、サブリース会社は収益源を失うことになります。また、管理が行き届かずに契約解除になった場合、サブリース会社の信用問題にもなりかねません。その場合、新たな顧客を見つけることが難しくなるでしょう。
転貸先の契約違反は、サブリース会社の経営に深刻な影響を与える可能性がありますので、賃貸管理の徹底が重要です。
転貸(サブリース)のリスクを回避するためには?
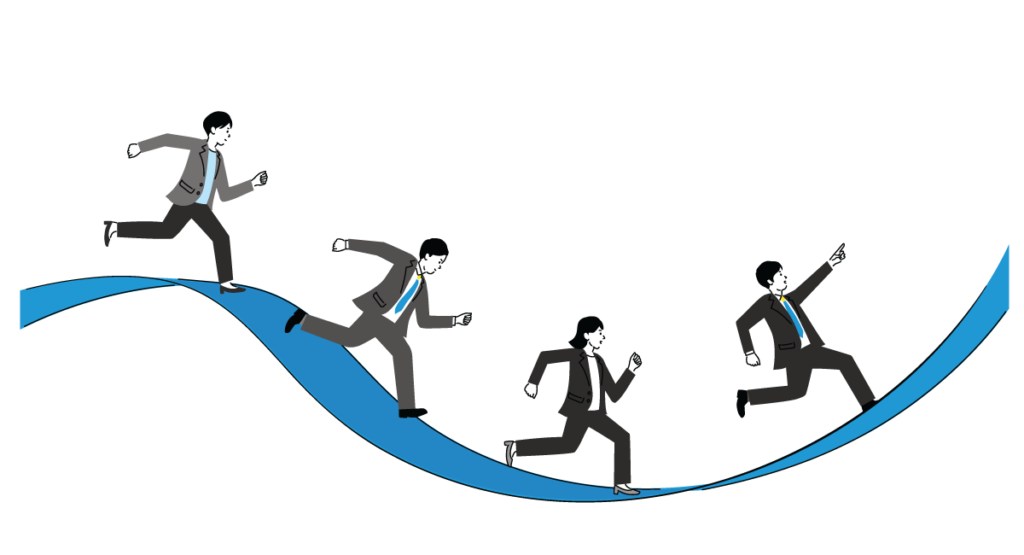
転貸(サブリース)のリスクを回避するためのポイントは以下のとおりです。
- 貸主の承諾を書面で明文化する
- 転借人の信用調査を実施する
- 原状回復の義務を明確にする
- 賃貸保証会社を活用し、未回収リスクを低減する
転貸(サブリース)におけるリスクは、適切な契約管理とリスクを回避することが可能です。以下で、具体的な対策について解説します。
貸主の承諾を書面で明文化する
転貸(サブリース)のリスクを回避するためには、オーナーとの取り決めを書面で取り交わすことが重要です。書面にすることで転貸の許可を得た法的な証拠にすることができます。
転貸(サブリース)を行う際には、事前にオーナーの承諾を得ることが民法で義務付けられています。用途(居住用、事業用など)、期間(何ヶ月または何年までの期間で転貸するか)などの条件を契約書に明記する必要があります。
さらに、契約書に加えて承諾書を別途作成し、オーナーから署名と押印をもらうことをおすすめします。というのも、この承諾書は、後々発生する可能性があるトラブルなどに対して強力な証拠となりうるからです。例えば、オーナーが転貸を拒否した場合に、事前に許可を得ていたことを証明するための重要な手段となります。
こうした書面での取り決めをきちんと行うことで、転貸に関するすべての合意が法的に有効となり、予期しないリスクや紛争を避けることができるでしょう。
転借人の信用調査を実施する
契約前に転借人の信用調査を実施したうえで、転貸によるリスクを事前に見極めておくことが重要です。転借人(実際に物件を利用する人や企業)の支払能力が低いと、賃料滞納が発生し、転貸契約自体が破綻するリスクが高まります。
信用調査を行う際のポイントは以下のとおりです。
<法人の場合>
- 決算書や財務諸表の確認(経営状況の確認、負債の程度を把握)
- 取引先や業界での評判(過去の倒産歴や信用トラブルを確認)
- 事業計画の妥当性(転借人のビジネスの安定度) など
<個人の場合>
- 勤務先、年収の確認(安定した収入があるか)
- 信用情報の確認(過去の滞納歴や破産歴の有無)
- 連帯保証人の有無(万が一の際に代わりに支払える人がいるか) など
原状回復の義務を明確にする
契約書で原状回復義務の所在を明確にしておくことも、転貸(サブリース)のリスクを回避するためのポイントの一つです。
契約書には「勝手な改装や設備変更を禁止する」(必要な場合は貸主の許可を得る)などの文言を入れておくことで、転借者に勝手にリフォームされてしまうといったケースを防ぐことができます。
特に事業用物件は、改装を伴うケースが多いため、細かいルールを定めておくことが重要です。保証金や敷金を適切に設定しておくと良いでしょう。
違法転貸を防ぐ管理体制を整える
転貸(サブリース)のリスクを避けるためには、管理体制を整えて違法転貸を防ぐことも重要なポイントです。
違法転貸を防ぐためには、契約書に違法転貸を禁止する条項を盛り込むことが求められます。転貸禁止、用途制限を明記し、違反が発覚した場合は契約を即時解除するといった ペナルティ・損害賠償の規定などを盛り込みます。
また、物件のチェック体制を整えることも重要です。定期巡回・内覧チェックはもちろんのこと、近隣住民からの情報収集なども徹底します。違法転貸が発覚した場合は、証拠を確保した上で、即時解約および退去を求め、場合によっては損害賠償請求を検討するなど、迅速な対応が求められます。
賃貸保証会社を活用し、未回収リスクを低減する
転貸業者はオーナーに賃料を支払う義務があります。そのため、賃貸保証会社を活用することで、転借人の経営破綻などによる賃料の未払いリスクをできるだけ回避するようにしておくことが重要です。
賃貸保証会社は、転借人が賃料を滞納した場合、転借人に代わって賃料を支払い、督促・回収を代行します。転借人の信用審査なども請け負うため、転借人の滞納リスク自体を事前に低減することができるでしょう。
なお、賃貸保証にはさまざまなプランがあります。そのため、保証内容(最大保証額、滞納時の立替期間など)を確認したうえで、最適なプランを採用することがポイントです。
転借人には、保証会社の加入を義務付けるのに加えて、滞納時の回収プロセスを契約書に明記(催告期間、保証会社への請求手続き)することも求められます。
賃貸保証会社については以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
関連記事:賃貸保証会社とは?審査の流れや費用相場、メリット・デメリットも解説
賃貸管理業務のクラウドサービスを活用する
転貸(サブリース)のリスクを低減するためには、賃貸管理業務の質を改善することも重要です。例えば、契約・入居者管理を一元化すれば、情報の可視化と共有が進み、さまざまなリスクに迅速かつ漏れなく対応できるようになるでしょう。滞納有無や滞納期間の一覧化、督促状の一括出力など、効率的な督促管理を実現も可能です。
賃貸管理システム『いい生活賃貸管理クラウド』は、不動産管理会社やオーナー様向けのクラウド型賃貸管理サービスです。物件管理、賃貸契約、入出金管理など、賃貸管理業務のさまざまな業務を一元管理することができます。転借人から預かった共益費などを不動産オーナーへ自動送金する「サブリース預り金送金機能」を実装し、支払業務を漏れなく、効率化することが可能です。
転貸(サブリース)のメリットとリスクをより深く理解しよう

不動産業における転貸(サブリース)は、収益力の向上や幅広いニーズへの対応といったメリットがあり、ビジネスチャンスを広げる手段の一つとなるでしょう。その一方で、契約内容や管理を誤ると大きなトラブルを招く可能性があります。
転貸(サブリース)を適切に運用するためには、契約内容の明確化に加えて、適切な賃貸管理の体制を整えることが欠かせません。不動産賃貸管理のクラウドサービスを活用すれば、これらのリスクを一元管理し、効率的に運用することができるはずです。賃貸管理システム『いい生活賃貸管理クラウド』を導入することで、物件管理、賃貸契約、入出金管理など、賃貸管理業務のあらゆる業務を一元化し、効率的で正確性の高い賃貸管理業務を実現できるでしょう。
・執筆者

株式会社いい生活 マーケティング本部
マーケティング部
広報部
全国の不動産市場向けイベント、セミナーなどにて多数登壇、皆様のお役に立つ最新情報を発信しております。


