
賃貸物件で賃料の滞納が発生すると、収益の悪化につながります。そのため、必要に応じて借主に督促を行い、賃料の早期回収を試みる必要があります。督促を適切に行うことで、滞納の長期化や強制退去を防止することができるでしょう。
その一方で、督促の方法によっては違法となる可能性もあるため、賃料回収にはリスクが伴うともいえます。借主とのトラブルを避けるためにも、賃料の督促には細心の注意を払わなければいけません。
そこで今回は、督促を実施する際の注意点、督促を防ぐためのポイントなどについて解説します。賃料滞納時の督促のポイントを把握し、適切な賃貸管理を実現しましょう。
賃貸管理における督促とは?
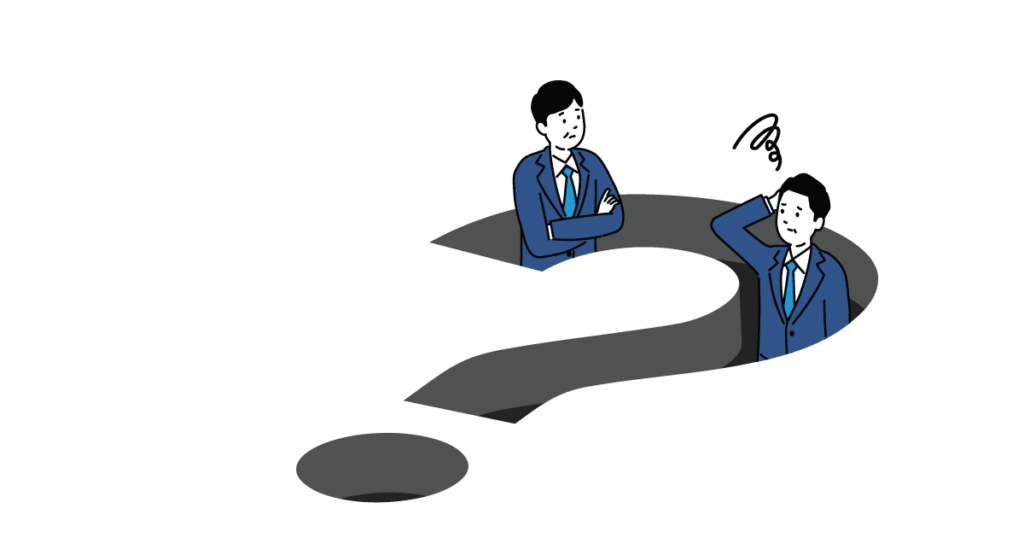
督促とは、契約に基づく賃料や代金が支払われなかった場合、借主に書面や電話などで通知し、支払いを促すことを指します。特に賃貸借契約においては、賃料の滞納が続くとオーナーの収益が悪化するため、経営状態の悪化につながります。
滞納は、借主の単なる支払い忘れの場合もあります。しかし、これが繰り返されると、賃貸管理業者とオーナーの信頼関係が損なわれることにもつながりかねません。賃料回収の流れはある程度決まっていますので、必要に応じて適切な督促を行うことが重要です。
督促と催促の違い
催促とは、契約上の支払期日を過ぎた場合に、早期の支払いを求める行為です。督促は主に金銭の支払いを求める行為ですが、催促は金銭の請求以外にも使われる場合があります。例えば、「上司から業務概況の報告を催促された」というように、金銭の支払い以外のシーンでもしばしば使われます。
督促には強制力があり、場合によっては法的措置に発展することもあります。しかし、催促は相手に対して柔らかく接し、自発的に動いてもらうための要求といえるでしょう。これが督促と催促の相違点です。
賃料の滞納があった場合は、まず催促によって支払いを促し、相手が応じないときに督促へと移行します。催促を行わずにいきなり督促すると、トラブルに発展する恐れがあるため、注意が必要です。
督促の流れ
一般的な督促の流れは次の通りです。滞納賃料の回収手続きは、借主への通知から始まります。
- 支払期限の経過を通知する
- 第1回目の正式な督促を行う
- 再度の督促を行う
- 法的措置の準備を開始する
いきなり強く督促するのではなく、まずは滞納を防ぐために、入居者に事前に注意を促します。督促の際には支払いの期日も設定し、それでも応じないときは法的措置の検討も必要になるでしょう。
支払期限が経過したことを通知する(翌日〜数日以内)
賃料の滞納があった場合は、借主に支払期限が過ぎたことを通知します。通知は滞納日の翌日から数日以内に行い、電話やメール、SMSなどの手段で支払いの意思を確認します。
初回の賃料滞納はうっかりミスの可能性もあるため、「すぐに賃料を支払え」といった強い態度は避けるべきです。「お支払いの確認をさせていただきます」といった表現で、丁寧に対応しましょう。
一方で、通知が遅れると、借主は「少しくらい遅れても大丈夫」と考えるようになるかもしれません。その場合、賃料の滞納が繰り返されるといった可能性があるため、注意が必要です。通知の際には支払日と支払方法を必ず確認するようにしましょう。
第1回目の正式な督促を行う(1週間程度経過後)
支払期限を過ぎても賃料の入金が確認できない場合は、最初の督促を行います。借主に督促状や催告書を送付し、速やかな支払いを求めます。
督促状や催告書の文面には、次の内容を記載する必要があります。
- 賃料の入金が確認できていないこと
- 早急な支払いが必要であること
- 指定する支払期限と振込先
借主から連絡があった場合は、滞納の理由や支払いの意思について確認します。借主が経済的に困窮している場合は、分割払いや支払猶予の提案を検討することも可能です。行き違いで入金されている可能性もあるため、過度に強い表現は避けるようにしましょう。
再度の督促を行う(滞納1カ月経過)
再度の督促を行う際は、配達証明付きの内容証明郵便を送付するのが一般的です。内容証明郵便とは、いつ・誰が誰に対して・どのような文面を送付したのか、郵便局が証明するサービスです。
期限を過ぎても支払いがなく、最初の督促状にも反応がない場合、借主に支払う意思がないと判断される場合があります。そのような状況も想定し、配達証明付きの内容証明郵便を送付しておけば、「督促状を受け取っていない」といった言い逃れを防ぐことができるでしょう。
また、再度の督促では確実な支払いを促す必要があります。そのため、期日を守れなかったときは、連帯保証人や賃料保証会社に連絡する旨も記載しておくことが重要です。賃料滞納がさらに続くようであれば、両者に連絡を取り、法的措置の検討も必要になります。
法的措置の準備を開始する(滞納2〜3カ月経過)
賃料の滞納から2~3カ月経過した場合は、法的措置の検討を進めます。法的措置には以下の種類がありますので、何が最も効果的なのかに重点を置いて検討を進めていきましょう。
- 支払督促
- 少額訴訟
- 明け渡し訴訟
支払督促の手続きは申立書の提出のみとなっており、訴訟費用も比較的少額です。裁判所から督促状が送付されるため、法的効力を持つ通知となります。
滞納額が60万円以下の場合は、少額訴訟も有効な方法といえるでしょう。ただし、裁判官が和解を求めるケースが多く、賃料の減額や分割払いで決着する場合もあります。
賃料の滞納が3カ月以上になると、賃貸借契約の解除通知を送付し、応じない場合は明け渡し訴訟を検討します。最終手段として強制執行の申し立てが必要になるケースもあるため、弁護士に相談しながら進めるようにしましょう。
督促時の注意点とは?
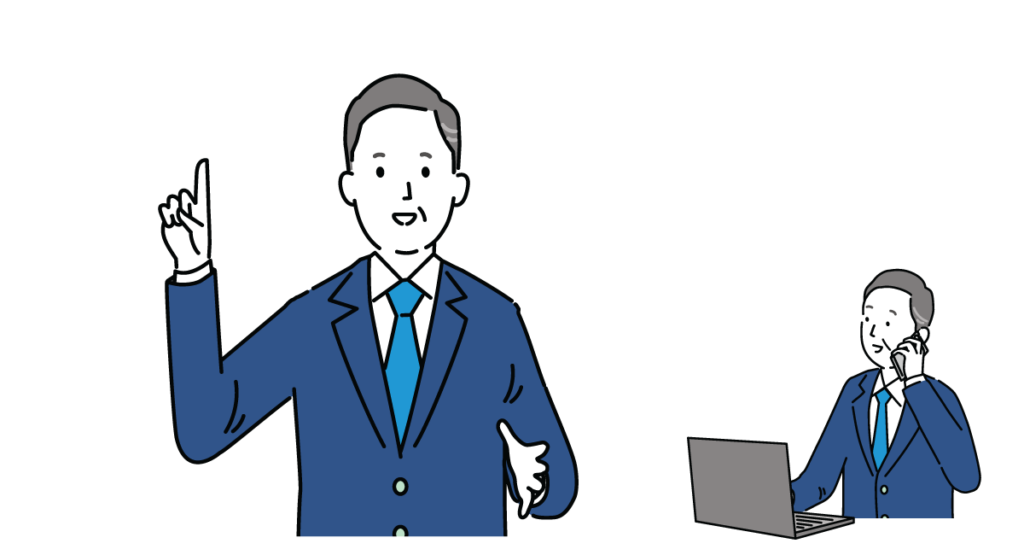
滞納賃料を回収する場合、直接取り立てを行うことは不可能です。法的措置を取らない限り、督促によって自発的な支払いを促すしかありません。
しかし、過度な督促は違法行為となる可能性があるため、賃料の回収は法律に準拠して対応することが求められます。場合によっては弁護士などの専門家や賃料保証会社と連携することも必要です。
賃料の滞納を督促するときは、以下の注意点をよく理解しておきましょう。
法律に基づいた対応をする
賃貸管理業者が賃料を督促する際は、貸金業法や消費者契約法に抵触しないように注意する必要があります。以下のような方法で督促した場合、違法行為になる可能性があります。
- 借主の勤め先に督促電話を入れる、または訪問する
- 早朝や深夜に電話や訪問で督促する
- 借主の部屋に居座って督促する
- 玄関ドアに「賃料を支払え」などの貼り紙をする
- 借主の家族や友人などに督促する
- 威圧的な態度で督促する
- 部屋の鍵を無断で交換する
借主以外の第三者(家族、友人など)に滞納の事実が知られるような督促行為は、プライバシー侵害や違法行為とみなされる可能性があります。勤め先に電話で督促する行為や、貼り紙なども注意が必要です。正当な理由がなく、21時頃から翌朝8時頃の時間帯に督促することも認められていません。
適切な連絡方法を選ぶ
督促の初期段階では、電話やメール、SMSや書面などで借主への通知を行います。滞納理由がうっかりミスで、借主に支払う意思があれば、速やかに賃料を回収できるでしょう。
ただし、訪問で督促する場合は注意が必要です。「突然押しかけてきた」などと思われないよう、事前に訪問日を連絡し、借主の了承を得るようにしましょう。
訪問すると一定の圧力がかかります。そのため、借主には丁寧な態度で接し、強引な取り立てだと思われないように注意しましょう。対面で話し合う際は、メモや録音でやりとりの記録を残すようにします。
保証会社や弁護士と連携する
借主が督促に応じない場合、保証会社や弁護士との連携が重要になります。都市部の賃貸物件では、家賃保証会社と契約しているケースが一般的です。滞納が発生した場合、保証会社がオーナーへの支払いを立て替えます。家賃保証会社と連携すれば、賃料をスピーディーに回収することができるでしょう。
家賃保証会社と契約していない場合は、弁護士に相談する必要があります。例えば、法律事務所名で内容証明郵便を送付すると、借主がすぐに支払うといったケースがあります。弁護士の介入によって、法的措置を回避しつつ、賃料回収を促進する効果が期待できるでしょう。
居住権の保護に留意する
賃料の滞納を督促する際は、借主の居住権への配慮も必要です。借地借家法では借主の「住む権利」を居住権として定め、手厚く保護しています。
賃料の滞納は重大な契約違反ですが、借主が収入確保などの改善に努めている場合、賃貸管理会社も信頼関係の修復に努めることが求められます。短期間の滞納にもかかわらず、無断で鍵を交換したり、荷物を撤去したりすると違法となる可能性があるため注意が必要です。
滞納が常態化し、強制退去を求める場合は、合意書を作成するなど、退去交渉を慎重に進める必要があります。
督促を防ぐためのポイント

賃料の督促には法的リスクが伴うため、適切な対応が不可欠です。しかし、そもそも滞納が発生しなければ、督促をする必要も生じません。そのため、滞納を防ぐための対策を講じることはさらに重要といえるでしょう。
ここでは、賃料の滞納を防ぐためのポイントとして、入居審査の強化や賃貸管理業務の効率化による漏れのない支払管理について解説します。
入居審査を強化する
賃料の滞納や督促を減らすためには、入居審査の強化が必要です。借主の職業や収入状況、勤務先を確認し、賃料の支払能力があるかどうかを見極めましょう。
会社員の場合は、直近3カ月の給与明細や源泉徴収票で所得を確認します。フリーランスや個人事業主と契約を結ぶときは、確定申告書の写しで所得を確認する方法もあります。
自営業者の収入は安定しないケースがあるため、確定申告書などの収入証明は過去3年分を確認するようにしましょう。賃貸借契約を締結する際は、連帯保証人や保証会社の利用を義務付け、借主が滞納しても賃料を確保できるようにしましょう。
賃料支払いの仕組みを整える
賃料の支払いの仕組みを整えることで、滞納のリスクを軽減することができます。滞納時の対応ルールを明確化すると、回収までのスケジュール管理がしやすくなるはずです。
物件によっては、賃料を現金手渡しで支払うケースもありますが、可能であれば口座振替に切り替えた方がよいでしょう。
賃料を口座振替にすると、毎月決まった日に指定口座へ入金されます。ただし、金融機関の都合で、口座振替は毎月27日となることが一般的です。借主の給与支給日が月末や月初だった場合、滞納が発生しやすくなります。口座振替が難しい場合は、クレジットカード決済やスマホ決済を導入するとよいでしょう。
管理システムや決済サービスを活用する
賃料の滞納理由で最も多いのが「支払い忘れ」です。支払期日の管理が不十分な場合、支払い忘れが常態化してしまうといったことも考えられます。そのため、賃貸管理システムや決済サービスなどを導入し、賃貸管理を漏れなく行うことが重要です。
賃貸管理システムを導入することで、入金情報の自動追跡ができるようになり、督促状の発行なども速やかに行えます。借主と管理会社の双方で期日管理を行うことで、賃料の滞納や支払い忘れのリスクを大幅に低減することが可能です。
また、スマホ決済などを借主に利用してもらうことで、手元に現金がない場合でも賃料の支払いがスムーズに完了させることができます。その際、決済用コードを読み取る手間がありますが、利用額に応じてポイントが貯まるなど、借主にもメリットがあります。
不動産管理会社や賃貸オーナー向けのクラウド型賃貸管理サービス『いい生活賃貸管理クラウド』は、オーナーや借主などの顧客情報や取引先を一括管理することが可能です。滞納の有無や滞納期間を視覚的に把握することができ、督促状などの一括作成も可能なため、業務効率化による漏れのない賃貸管理業務を実現することができます。
また、『いい生活Pay』は、不動産市場のDXを推進する株式会社いい生活の決済サービスです。請求は、URLをメールやSMSで送るだけのため、請求書の印刷や郵送の手間を省くことができます。口座登録や来店も不要で、簡単に支払いを済ませることができるほか、口座振替の登録もスマートフォン上で完結することが可能です。
滞納に対する早期の対応を徹底する
滞納が発生した場合は、早期の対応を徹底することが重要です。1回目の督促を迅速に行い、滞納を長引かせないようにすることが求められます。上で述べた「督促の流れ」「督促時の注意点とは?」に留意しつつ、督促のプロセスを進めていきましょう。
なお、督促状の送付などを怠った場合、支払期日から5年経過すると時効が成立します。借主が時効の援用を主張すると、家賃を請求できないため、「督促は期限付き」と理解しておくことが大切です。
また、借主が多重債務者だった場合は、自己破産する可能性もあります。自己破産は家賃の支払義務が免除されるため、回収は困難です。家賃を督促するときは借主の事情を把握し、必要に応じて分割払いや支払猶予を検討するようにしましょう。
賃料滞納への督促のポイントを把握し、適切な賃貸管理を実現しよう
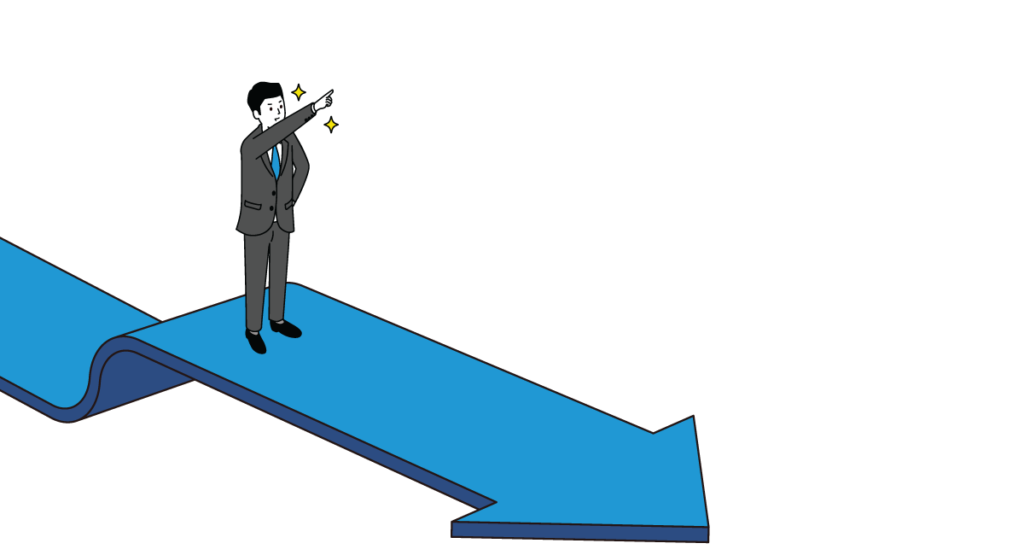
賃貸管理を円滑に進めていくためには、督促の際に適切な手続きを踏むことが重要です。法的リスクを避けつつ、早期対応を徹底することで滞納を防いでいくことが求められます。
賃料の滞納は、賃貸管理において避けられないリスクの一つです。しかし、適切な対応を行うことで、そのリスクを最小限に抑えることも可能です。滞納を防ぐためのポイントとして、入居審査の強化、賃料支払いの仕組みを整備することなどが挙げられます。
加えて、業務効率化による漏れのない賃貸管理体制を整備することも大切です。賃貸管理システム『いい生活賃貸管理クラウド』や『いい生活Pay』などのツールを活用し、デジタル化によって賃貸管理業務の質をさらに高めることがポイントとなります。ぜひ、ご検討ください。
・執筆者

株式会社いい生活 マーケティング本部
マーケティング部
広報部
全国の不動産市場向けイベント、セミナーなどにて多数登壇、皆様のお役に立つ最新情報を発信しております。


