
買取再販や新築分譲、土地分譲などを展開する不動産会社にとって、仕入れ案件をどう確保していくかは大きな課題です。所有者へのDMや一括査定、地主訪問など、一般所有者へのアプローチも有効です。しかし、物件を継続的に確保するためには、不動産会社からの買取相談を増やすことが欠かせません。
そのなかで接点が生まれるのが、宅建業の免許を持たない「不動産ブローカー」です。不動産ブローカーは一見すると、さまざまな人脈を持った有力な情報源です。しかし、報酬の受け取り方や関与の仕方によっては宅建業法違反とみなされてしまうリスクもあります。
この記事では、不動産ブローカーの定義や仲介業者との違い、違法とされる行為の判断軸、報酬の仕組みなどを整理しました。不動産会社からの紹介案件を増やすうえで、ブローカーとの関わり方に迷っている方へ、取引可否の判断に役立つ実務的な視点をお伝えします。
不動産ブローカーとは
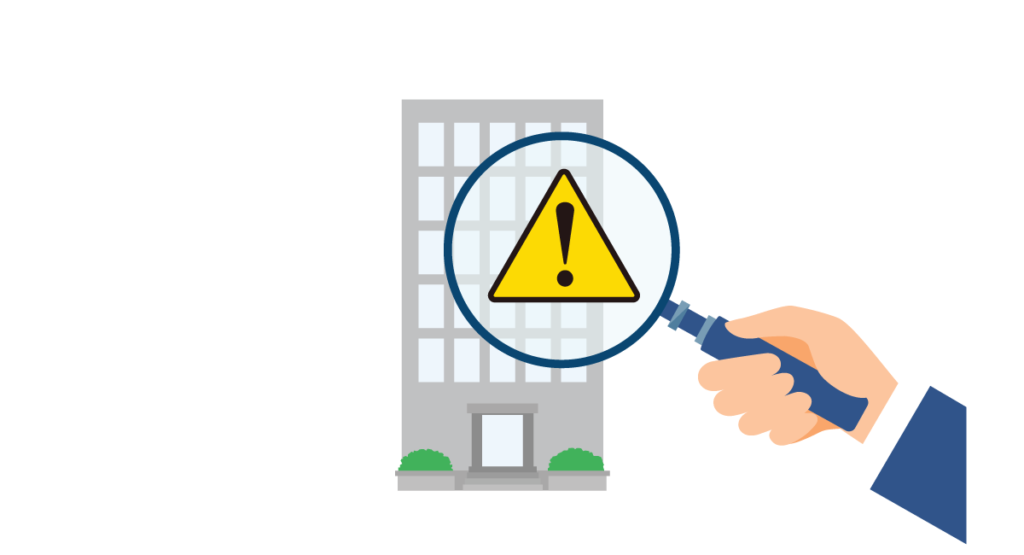
不動産ブローカーは、宅建業の許可を得ずに物件情報や買主・売主を紹介し、報酬を得ています。正規の仲介業者とは異なり、宅建業法の枠組みの外で活動していることが特徴です。そのため、責任の所在や情報の正確性が不透明になりがちです。
不動産ブローカーと関わる場合は、違法性の有無やリスクを正しく理解しておきましょう。この記事では、不動産ブローカーと仲介業者の違い、違法とされる行為、実態などについて整理します。
不動産ブローカーと仲介業者の違い
不動産仲介業者は、宅地建物取引業の免許を取得し、宅建業法に基づいて営業しています。契約時には重要事項説明や書類作成などが義務づけられており、法的責任の所在も明確です。
一方の不動産ブローカーは、免許を持たずに売主や買主、物件情報などを紹介し、成約時に報酬を受け取ることが一般的です。宅建業法の適用範囲外で活動しているため、業務内容や責任の範囲に明確なルールがありません。活動の実態が外部から見えにくいといえるでしょう。
なかには不動産会社と非公式に関係を築き、水面下で取引の調整に関与し、未公開物件や大型案件を取り扱う事例もあります。
不動産ブローカーの違法性は?
不動産ブローカーが物件情報を提供したり、売主や買主を紹介したりするといった行為は、それ自体では違法とはみなされません。というのも、契約締結や重要事項の説明といった宅建業法上の業務を行わなければ、宅建業の許可は不要とされているからです。
ただし、情報提供や紹介に対して報酬を支払う場合は注意が必要です。たとえ「情報提供料」や「業務協力費」などの名目であっても、実質的に仲介行為とみなされる場合は、宅建業法違反と判断される可能性があります。
宅地建物取引業法第12条第1項では「免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない」と定められています。ここでいう宅地建物取引業とは、不動産の売買や交換、賃借の代理・媒介を業として反復継続的に行うことを指します。
無免許でこれらの行為を行えば、法律に抵触し、行政処分や刑事罰などの法的責任を問われるおそれがあります。
不動産ブローカーの年収はどのくらい?
ここからはあまり知られていない不動産ブローカーの実態、とりわけ収入についてご紹介していきます。
不動産ブローカーの報酬は、紹介先の不動産会社が得る仲介手数料の一部から支払われます。物件が成約した際に、手数料の10〜50%程度を受け取るのが一般的です。報酬の割合は案件ごとに異なるため、業務量や交渉力によっては50%を超える場合もあります。
たとえば、3,000万円の売買物件が成約した場合、不動産会社が受け取る仲介手数料は約105万円(3%+6万円+消費税)です。このうちの10〜50万円前後が不動産ブローカーに分配されます。
不動産ブローカーの年収は、扱う案件の規模や件数によって大きく変動します。安定的に成約を重ねられれば、年収1,000万円を超えることも珍しくありません。なかには、大型案件数件で数千万円を得る人や、年間1億円超の報酬を得る不動産ブローカーも存在します。
アメリカの不動産ブローカーとの違い

アメリカでは、不動産ブローカーは国家資格として位置づけられています。医師や弁護士と並ぶ高度な専門職として広く認知されており、社会的地位や信用も高いことが特徴です。
アメリカで不動産ブローカーになるためには、大学や専門学校で規定科目を履修したうえで、受験資格を得る必要があります。試験の難易度も高く、高度な専門知識が求められます。
なお、アメリカでは不動産ブローカーと不動産エージェントに分かれており、前者は事務所を開業することが可能です。エージェントは営業担当として活動し、ブローカーと契約を結び、報酬の一部をブローカーに支払います。
日米の不動産ブローカーの位置づけは、資格制度・組織構造ともに大きく異なります。そのため、不動産ブローカーに対する社会的な認識や責任の範囲にも明確な違いがあるといえるでしょう。
不動産ブローカーを使うリスク

物件の仕入れや集客の一手段として、不動産ブローカーから情報提供を受ける機会も少なくありません。その場合は、不動産ブローカーを利用することで生じるトラブルについて、あらかじめ把握しておくことが大切です。
特に、宅建業の免許を持たない不動産ブローカーとやりとりする際は注意が必要です。契約や金銭授受の場面で、責任の所在が不明確になりやすいためです。万が一、トラブルによる損害が生じた場合でも、補償が受けられないケースもあります。
ここでは、不動産実務の中で起こり得る具体的なリスクとその背景を整理し、注意すべきポイントについて解説します。
手付金を騙し取る
不動産ブローカーが「先に手付金を支払えば物件を押さえられる」と買主に直接持ちかけるケースがあります。不動産会社を通さず、ブローカーに直接現金を渡した結果、返金されなかったという被害が報告されています。
このような金銭トラブルが発生した場合、不動産会社にも説明責任が及ぶおそれがあります。特に、無免許の人物が金銭のやりとりに関与していた場合、取引全体の信頼性が損なわれかねません。
一見すると合法に見える取引であっても、内容によっては大きなリスクを伴います。情報の出どころや金銭の流れを明確にし、関係者の立場と責任範囲を慎重に確認することが不可欠といえるでしょう。
コンサルティング料金の請求
不動産ブローカーとのやりとりでは、「コンサルティング料」などの項目で、根拠の不明確な金銭を求められるトラブルが発生することがあります。
たとえば、物件情報の紹介にも関わらず、「調査や交渉を支援した」と主張され、報酬を求められるケースなどです。実際にはそれらについて相談も依頼もしておらず、合意もない状態で、既成事実であるかのように請求されることがあります。
ブローカーの中には、自身を「不動産コンサルタント」と名乗る者もいますが、多くは無資格であり、業務の中身もあいまいです。肩書きに惑わされることなく、具体的にどのようなコンサルティングをしているのかなどを確認するようにしましょう。
被害を受けても補償されない
不動産ブローカーが関与した取引では、万が一トラブルが発生した場合でも、補償を受けられないケースが多く見られます。
宅建業者であれば、保証協会に加入していることが一般的です。保証協会は、不動産会社が倒産などで契約不履行に陥った際、あらかじめ預託された分担金を使って弁済する制度を提供する団体です。また、多くの不動産会社は損害保険にも加入しており、取引上の過失による損害についても一定の補償が期待できます。
一方、ブローカーは宅建業者ではないため、こうした制度に加入していません。持ち逃げや不適切な金銭授受があった場合でも、補償はなく、損失は取引当事者の自己責任として処理されることになります。
トラブルの内容によっては、不動産会社側にも説明責任が及ぶおそれがあります。特に無免許の人物が関与していた場合、取引全体の信頼性が問われることになるでしょう。顧客や関係者からの問い合わせや指摘に対応しなければならなくなります。
こうしたリスクを未然に防ぐためにも、ブローカーが関与する取引には慎重に対応することが求められます。
物件を仕入れる際のポイント

不動産の仕入れ業務では、情報の信頼性や適切な取引相手を見極める力が問われます。
特に未公開物件や不動産ブローカー経由の案件は、正確な情報の見極めとリスク管理が欠かせません。免許の有無や取引相手の姿勢を見極めるとともに、提供された情報に対して冷静かつ迅速に対応する姿勢が大切です。
ここでは、仕入れ業務を進めるうえで押さえておきたい基本的なポイントを整理します。
宅地建物取引業者かを確認する
上でご紹介した通り、不動産ブローカーとの取引の場合、いくつかの深刻なリスクがあります。そのため、トラブルを避けることを重視するのであれば、正規の宅建業者を通じて取引を進める方が無難といえるでしょう。
取引先が宅建業の資格を保有しているかどうかは、都道府県の宅地建物取引業者名簿で確認することが可能です。免許の有無に加え、行政処分歴なども公開されているため、信頼性を判断する材料となります。
登録の有無だけでなく、実際の対応姿勢や情報の確実性も踏まえて、取引先を慎重に選定することが求められます。
情報を鵜呑みにしない
不動産ブローカーは、住宅メーカーや地元不動産会社はもちろんのこと、地主や士業などの幅広い人脈から情報を得ています。ただし、仕入れた情報の価値は不動産ブローカーのスキルや人脈に依存するため、ばらつきがあるのが実態です。
なかには、売れ残り物件を「お得な情報」として紹介してくるケースもあります。たとえ魅力的に見える情報であっても、裏付けを取らずに判断するのはリスクが高いです。
紹介された物件については、価格の妥当性や過去の販売履歴、現地の状況などを必ず確認し、冷静に判断することが大切です。
信頼できるパートナーを選定する
不動産ブローカーに限った話ではありませんが、仕入れ先の信頼性を見極めることは極めて重要です。情報に裏付けがあり、問い合わせにも丁寧に対応してくれる取引先とは、自ずと長期的な関係が築かれていくでしょう。
反対に、高圧的な態度の相手とは、交渉が一方的になりやすく、意思疎通の齟齬が起こるおそれがあります。「案件を回してやっている」といった姿勢の取引先とは、対等なやりとりが難しく、安定した仕入れは期待できません。
かつては接待や贈答品で関係を深める手法もありましたが、今日では、成果と信頼を重視して取引先を選ぶことが一般的です。対応力や誠実さを見極めながら、信頼できる相手と健全な関係を築くことが、仕入れ業務の安定につながります。
スピーディーな対応を心がける
信頼できるパートナーと関係を築くためには、物件情報を受け取った際の姿勢が重要です。紹介内容には前向きに向き合い、金額提示はできるだけスピーディーに行うようにしましょう。速やかに回答すれば、紹介元からの信頼獲得にもつながるはずです。
購入を見送る場合も、理由を明確に伝えるといった姿勢が欠かせません。返答があいまいな場合、次回以降の紹介が途絶え、仕入れの機会を失うといったリスクが考えられます。
こうした対応姿勢は、売主や仲介業者に限らず、すべての顧客に共通します。スピーディーかつ丁寧な応対は、営業担当者としての信頼に直結するといえるでしょう。
『いい生活売買クラウド 営業支援』は、営業担当者としての質の高い対応を支える営業支援ツールです。問い合わせへの自動返信や顧客情報の一元管理、来店予約の共有などにより、対応漏れや遅れを防ぎます。来店前後の対応を効率化できるため、営業業務全体の質を高めることが可能です。
仕入れの安定化、営業品質の向上を実現しよう

不動産ブローカーとの関わりは、物件の仕入れを安定させるうえで一定のメリットがあります。その一方で、責任の所在を不明確なままにやりとりを進めると、思わぬトラブルを招くおそれがあるため、注意が必要です。こうしたリスクを防ぐためには、取引の可否を見極める視点が欠かせません。情報の精度を確認し、リスクを正しく把握することがポイントとなります。
また、こうした対応は、相手の応対姿勢の見極めにもつながります。情報に裏付けがあり、問い合わせにも丁寧に対応してくれる取引先とは、関係性を積極的に築くべきです。こちらもスピーディーで誠実な応対を心がけることで信頼を獲得し、有益な情報を継続的に得やすくなる状況をつくっていきましょう。
こうした営業品質の向上には、『いい生活売買クラウド 営業支援』をはじめとする不動産営業支援ツールの活用が効果的です。リスクを抑えつつ、成果につながる仕入れ体制と営業品質の両立につなげることができます。
・執筆者

株式会社いい生活 マーケティング本部
マーケティング部
広報部
全国の不動産市場向けイベント、セミナーなどにて多数登壇、皆様のお役に立つ最新情報を発信しております。


