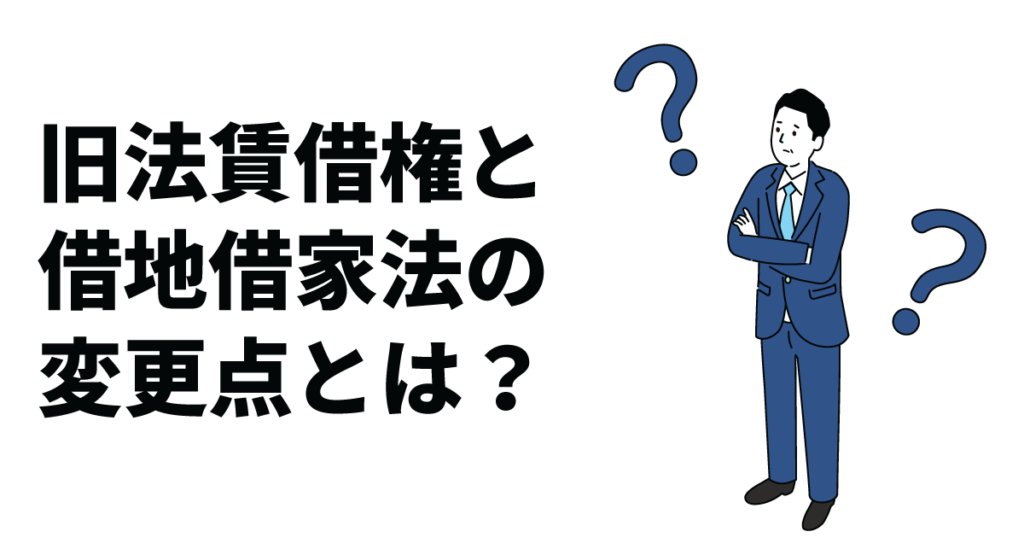
賃借権とは、その名の通り「お金を払って物を借りる権利」です。「借りる」という言葉から軽い権利と考えてしまいがちですが、不動産取引においては所有権と並ぶ重要な権利です。
土地を所有して賃貸しているオーナー(底地権者)と、その土地を借りて使う権利を持つ借主(借地権者)の権利の価値を比較すると、「借りる権利」の方が価値が大きいケースも少なくありません。
そこで今回は、不動産取引について知っておきたい賃借権のポイント、とりわけ、借地権・地上権との違い、旧法借地権と借地借家法の変更点などについて解説します。
賃借権とは?
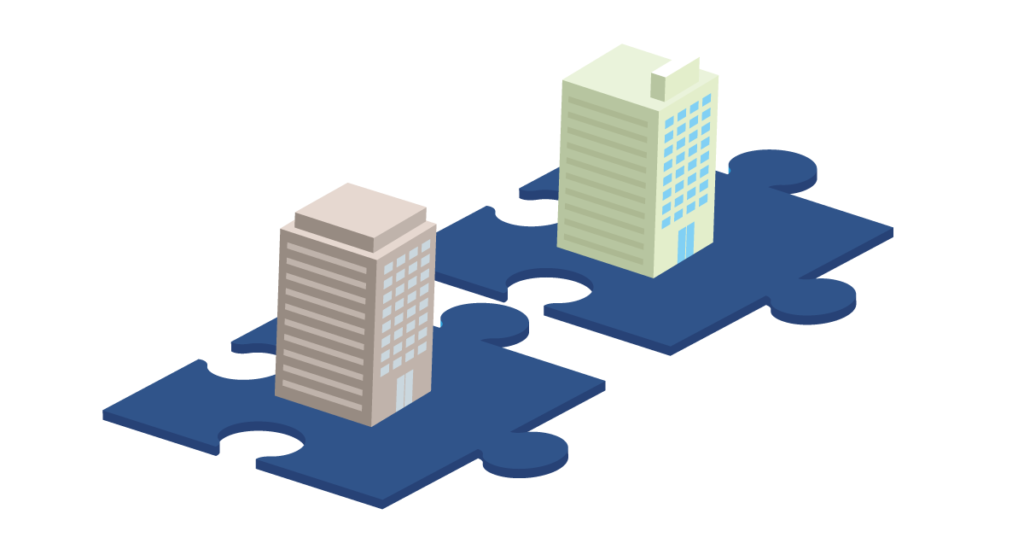
賃借権とは、他人が所有する土地を借り受け、その上に建物を建てて使用する権利を指します。
借地権が法律上で生じるのは、賃借人が土地を借りて建物を建てるケースで、駐車場のような更地のまま利用する場合は該当しません。というのも、移動や除却が難しく、かつ高額になりやすい建物という資産を介して発生する権利のため、単なる「物の貸し借り」に比べて厳格なルールが定められています。
また、1992年8月1日に施行された借地借家法によって権利の形や契約のルールが変化したため、同じ借地権でもそれが発生したタイミングによって借地法(旧法)が適用されるか、もしくは借地借家法(新法)が適用されるかが異なります。契約期間の定めなどに相違があるため、その点に着目して仕組みを理解することが重要です。
借地権・賃借権・地上権の違い
借地権とは、建物の所有を目的として地代(賃料)を支払って地主(土地所有者)から土地を借りる権利のことを指します。土地の所有権は地主が持ったままの状態であるものの、それを使用する権利は借地人(借地権者)が持ちます。
借地権には、大きく分けて「賃借権」と「地上権」の2種類があります。どちらも土地を借りて使用する権利ですが、自由度に差があります。借地権は、貸し手に対して「自分が借りている」と主張できる権利(債権)に過ぎません。しかし、地上権は第三者に対しても「自分が使う権利を有している」と主張できる権利(物権)です。
例えば、地上権は地主の許諾なしに建物を建てられるだけでなく、建物の売却や第三者への転貸も可能です。また、地上権自体を担保とした抵当権設定もできます。一方の借地権には地上権ほどの自由度は認められず、建物の建築や売却の際には地主の承諾が必要とされます。そのため、賃借権よりも地上権のほうがより強い権利といえるでしょう。
旧法借地権と借地借家法

借地権を理解するうえで重要なポイントの一つが、1992年8月1日に施行された借地借家法です。
旧法では借地人の権利が強く、地主が契約の更新を拒むことが困難だったため、地主の土地活用が阻害されていました。そのため新法では、契約期間の満了によって借りる権利が消滅する「定期借地権」が新たに設けられました。
ここでは、借地借家法で定められた普通借地権と定期借地権とともに、旧法が定める借地権についても解説します。
借地借家法が整備された背景
旧法のもとでは「一度借地権を設定すると、地主が半永久的に土地を利用できなくなる」という弊害がありました。というのも、契約期間についての定めはあるものの、正当な事由がなければ地主は更新を拒むことができなかったからです。
そのうえ契約終了時には、借地権者が地主に対して建物の買取を請求できる権利(建物買取請求権)が認められており、これも契約終了を阻害する要因となっていました。
このような背景から、賃貸人と賃借人の権利関係を見直す機運が高まっていきました。
旧法借地権の特徴
借地法(旧法)に基づく借地権、いわゆる旧法借地権では、契約の存続期間は借地上に建てる建物の種類によって異なります。
石造や土造、煉瓦造(鉄筋コンクリート造などを含む)など、「堅固の建物の所有」を目的とするときは30年以上と定められ、契約で30年未満の期間を定めた場合や期間の定めをしなかった場合は60年とみなされます。木造などの建物(いわゆる非堅固建物)の場合は20年以上です。
この期間は、地主・借主双方の合意があれば、さらに長期にわたって設定することも可能です。なお、期間満了後の更新については、堅固な建物は30年以上、非堅固な建物は20年以上と規定されています。
また前述の通り、「地主は正当事由がないと更新を拒絶できない」「借地権者は地主に対して建物買取請求権を行使できる」など、地主にとっては不利な点が多いことも特徴です。そのため、借地権の買戻しや明け渡し料の支払いなどを求められることも少なくありません。
旧法借地権は、借地借家法が施行される以前に契約した場合に限って適用される権利形態ですが、現在も適用されている物件が数多く存続しています。
新法借地権の特徴
新法借地権(借地借家法)に定める借地権では、旧法の借地権を踏まえて規定された「普通借地権」に加え、更新の定めがない「定期借地権」が規定されたことも重要なポイントです。
ここでは、普通借地権と旧法との違いや、新たに定められた定期借地権について詳しくみていきましょう。
①普通借地権
普通借地権は、旧法借地権と同様に契約の更新ができる借地権です。つまり、契約を更新することで土地を半永久的に借り続けられるということになります。
加えて、地主が更新を拒絶する場合に正当な事由が必要とされる点も旧法と同様で、「契約期間満了後に更新すること」が前提の権利といえるでしょう。
存続期間は建物の構造に関わらず30年以上で、期間を定めない場合は30年とみなされます。期間満了後の更新で必要とされる新たな存続期間は、初回の更新では20年以上、2回目以降は10年以上です。また契約満了時には、地主に対し建物を時価で買い取ることを請求できるとされています。
②定期借地権
定期借地権は、新法で新たにつくられた仕組みで、契約の更新がないことが特徴です。ただし更新がない代わりに、普通借地権と比較して存続期間が長めに設定されています。契約の存続期間は、特約の内容などによって一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権の3種類に区分されます。
一般定期借地権は、契約の存続期間を50年以上と定めることで、期間満了時の更新や建物買取請求権を認めず、土地を更地の状態に戻して地主に返還する仕組みの借地権です。一戸建てやマンションなど、住宅用として土地を賃借する際に利用されます。
事業用定期借地権は、店舗など事業用の建築物として利用するために土地を借りる場合の仕組みで、契約期間は10年以上50年未満です。契約終了後は一般定期借地権と同様に、建物を解体して更地にして返還する必要があります。
建物譲渡特約付借地権は、契約期間を30年以上と定め、満了後に建物を地主が買い取る旨の特約を付した定期借地権です。
旧法借地権と借地借家法の違い

1992年8月1日の借地借家法の施行によって制度化された借地権では、借地権設定者の権利保護の観点から解約の条件が明確化されました。旧法借地権と借地借家法の相違点について、順を追ってみていきましょう。
| 旧法借地権 | 普通借地権 | 定期借地権 | |
|---|---|---|---|
| 契約期間の定め | ・堅固建物 30年以上(30年未満の期間を定めた場合などは60年)・非堅固建物 20年以上・建物の種類・構造を定めなかったとき 30年以上 | 30年以上(期間を定めない場合は30年) | ・一般定期借地権 50年以上・事業用定期借地権 10年以上50年未満・建物譲渡特約付借地権 30年以上 |
| 契約更新の定め | あり(正当事由がないと拒絶できない) | あり(正当事由がないと拒絶できない) | なし |
| 契約満了時の建物の扱い | 建物買取請求権あり | 建物買取請求権あり | 解体して更地を返還(建物譲渡特約の場合は売り渡し) |
| 再建築 | 地主の承諾により可(建物の残存期間により借地権契約が延長) | 地主の承諾により可(建物の残存期間により借地権契約が延長) | 地主の承諾により可(借地権契約は延長されない) |
契約の更新
旧法に基づく借地権と、借地借家法に基づく借地権の大きな違いは、契約更新の有無です。
借地借家法に基づく借地権であっても、普通借地権であれば旧法借地権と同様に契約の更新が認められる一方で、新たに定められた定期借地権には契約の更新がありません。契約期間が満了すると借地権は消滅します。
定期借地権では、借地人は契約満了時に建物を解体して土地を更地に戻して返還する特約を結びます。また、建物を譲渡する特約を盛り込んだ契約を結ぶことも可能です。この場合は30年以上の契約期間を定めて、借地上の建物を地主に売り渡すことで契約が終了します。
建物の再建築
旧法借地権や普通借地権では、地主の承諾を得られれば建て替えが可能です。ただしその場合、地主に対して一定の金額を「承諾料」として支払う必要が生じることが一般的です。金額は、事前に契約で定めていなければ、地主と借主の話し合いで決定します。
ここで注意すべき点は「再建築により、借地権の残存期間が延長されること」です。地主の承諾を得て賃貸借契約の残存期間を超える建物を建てた場合には「借地権は、承諾があった日または建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続する」と規定されているため、自動的に契約期間が延長されます。
なお、地主の承諾が得られない場合、借地権者は裁判所に対して増改築許可の申立てをすることができます。裁判所が相当と認めれば、承諾に代わる許可を受けることが可能です。
このように借地人の権利が手厚い旧法借地権や普通借地権に対して、定期借地権の場合は再建築による契約延長は認められません。
賃借権の譲渡・転貸
賃借権は、地主の承諾があれば第三者に譲渡したり、転貸したりすることができます。これは旧法でも新法でも同様で、再建築の場合のように、地主に対して一定の承諾料を支払うことが一般的です。
一方で地主は、正当事由がない限り、この承諾を拒否することができません。拒否した場合、借地権者は裁判所に、地主の承諾に代わる許可を求めることができます。
また、地主の承諾を受けずに無断で賃借権の譲渡や転貸を行った場合、契約違反として賃貸借契約を解除される恐れがあります。
デジタル化が進んだ2022年5月の借地借家法の改正
2022年5月18日の借地借家法改正によって契約手続きのデジタル化が進みました。具体的には、これまで普通借地契約に限って認められていた電子契約が定期借地権契約にも認められるようになりました。
従来、定期借地権の特約に関する定めは「公正証書によるなど書面によってしなければならない」と規定されていました。しかし、「電磁的記録によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなす」と改正され、電子データでの契約書作成やオンラインでの契約締結が可能になっています。
ただし事業用定期借地権契約においては、「公正証書によってしなければならない」と定められており、電子契約は認められていません。
新旧賃借権の不動産業務におけるポイント

新たに結ばれる賃借権契約は新法(借地借家法)に基づいて締結されますが、旧法の時代に締結されて現在も存続しているケースも少なくありません。
旧法と新法の違いを深く理解することは、賃貸管理や借地権付き建物の売買などの業務で、安心安全な不動産取引を実現するために欠かせません。ここでは、新旧賃借権の不動産業務におけるポイントをご紹介します。
契約管理の適正化
旧法借地権は「建物が存続している限り使い続けられる性格の財産」である一方、定期借地権は「建物が使用できる期間も借地権の残存期間に限定される性格の財産」といえます。
そのため、こういった相違を正確に理解していなければ、顧客の要望に合致した提案をすることも、適切な契約内容を定めることもできません。
契約管理を適正に行うためにも、借地権付きの建物を扱う際には「新旧どちらの法律に基づいて設定された借地権か」、「新法であれば、どの形態の借地権か」を正確に把握し、法的な制約を十分に理解することが求められます。
リスク管理の強化
旧法借地権や普通借地権では、借地権の譲渡・転貸などに関しても借地権者に強い権利が与えられている一方で、地主の承諾が必要とされる手続きも少なくありません。
加えて、これらを承諾なしに行った場合は契約解除の要因となります。そのため、法的な制約に加えて、どういったリスクがあるのかを把握しておくことが重要です。また、地主と借地権者の良好な関係維持のためにも、前述した「承諾料」などについても理解を深めておくことも求められます。
顧客への適切なアドバイス
借地権は、売買契約によって買い手が自由に使用・処分できる所有権とは異なり、さまざまな制約があるため、不動産会社による長期的なサポートが欠かせません。
例えば、地代の負担や契約更新のルール、再建築の可否、売却や転貸の条件などが該当します。また、更新のない定期借地権の場合は、権利の内容を正確かつ詳細に説明することが求められます。
説明すべき項目・内容は多岐にわたりますが、借地権のメリットデメリットについて顧客がしっかりと理解して取引の可否を判断できる状態にすることが重要です。不動産会社にはそのためのサポートが求められます。
新旧賃借権の理解を深めよう

ここまで、不動産取引について知っておきたい賃借権のポイントとして、借地権・地上権との違い、旧法借地権と借地借家法の変更点などについて解説しました。
旧法賃借権と新法(借地借家法)の違いを深く理解することは、安心安全な不動産取引を実現するために欠かせないことがご理解いただけたかと思います。
顧客満足度向上のためには、不動産業務支援ツールを活用し、顧客ニーズに合った賃貸管理業務を展開することもポイントの一つです。賃貸管理システム『いい生活賃貸管理クラウド』は、物件管理、賃貸契約、入出金管理といったさまざまな賃貸管理業務の効率化を実現します。本文中でもご紹介した電子契約にも対応しており、『いい生活Home』、不動産オーナーアプリ『いい生活Owner』と連携させることで、入居者さまとの賃貸借契約、オーナーさまとの管理委託契約をワンストップで完結させることができます。ぜひご検討ください!
・執筆者

株式会社いい生活 マーケティング本部
マーケティング部
広報部
全国の不動産市場向けイベント、セミナーなどにて多数登壇、皆様のお役に立つ最新情報を発信しております。


