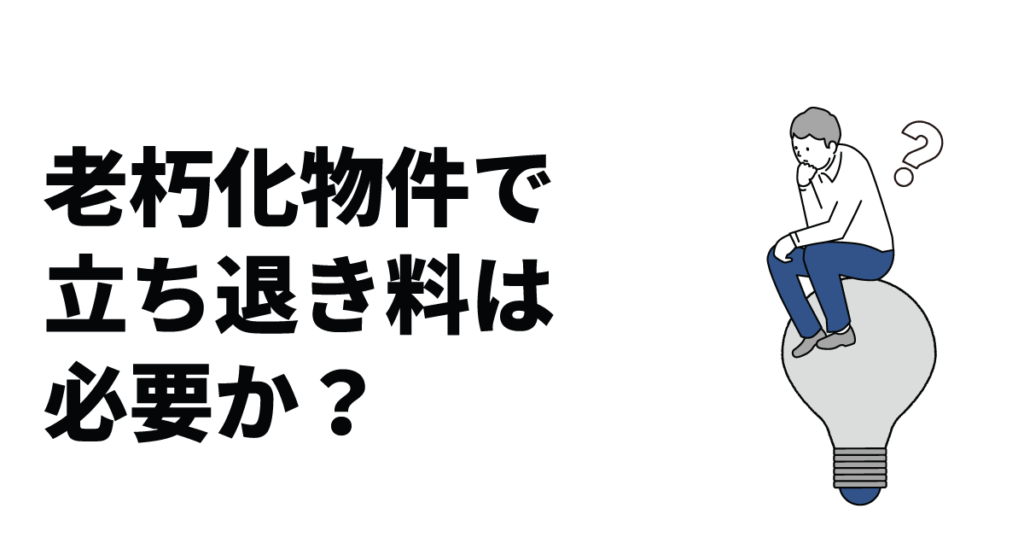
建て替えや取り壊しを検討する際、入居者への立ち退き交渉は避けて通れません。なかでも立ち退き料は、支払うべきか、いくらが妥当かといった判断に迷うものです。対応を誤れば、思わぬトラブルを招くおそれもあります。
立ち退き料は、法律で一律に決められているものではなく、借主との関係や物件の状況によって大きく変動します。交渉をスムーズに進めるためにも、基本的な考え方を押さえておくことが大切です。
この記事では、立ち退き料の相場や内訳、交渉の進め方に加え、老朽化物件の対応における注意点について解説します。
立ち退き料とは?

立ち退き料は、貸主の都合で物件の明け渡しを借主に求める際に、借主へ支払われる補償金です。引越し費用など、借主が立ち退きによって被る経済的損失を補う目的があります。
ただし、明け渡しを求めるたびに、必ず立ち退き料が発生するわけではありません。「正当な理由」が認められない場合に限り、補償として立ち退き料の支払いが必要と判断されることがあります。たとえば、貸主の一方的な事情による退去要請がその一例です。
立ち退きの正当な理由とは?

貸主が退去を求めるには、法律上「正当事由」が必要とされています。これは、一般的に言う「正当な理由」にあたるもので、裁判などで正当性が認められる事情を指します。
正当事由の例としては、建物の老朽化や契約違反などが代表的です。ここでは、正当事由と認められやすい具体例をご紹介します。
①建物の老朽化による耐震性の欠如
建物の老朽化が進み、居住に支障や危険が生じる可能性が高い場合は、正当事由と認められることがあります。
たとえば、現行の耐震基準を満たしていない旧耐震基準で建てられた建物などが該当します。また、設備の老朽化により修繕が困難な場合や、改修によって基準適合を目指す必要がある場合も正当事由と認められやすいです。
②借主が契約内容を遵守していない
借主の契約違反も正当事由となり得ます。たとえば、家賃の滞納やペット禁止物件での飼育といったルール違反がある場合です。また、共有部分の無断改変や、騒音・違法行為の疑いがある場合など、契約の継続が困難と判断されるケースが該当します。
③賃貸人または賃借人が建物を必要とする事情
貸主による自己使用の必要性も正当事由として認められることがあります。たとえば、転勤により遠方から戻ってきた貸主が物件を自ら使用する場合などです。家族構成の変化、親族の介護、事業利用なども該当します。
立ち退き料の内訳と相場
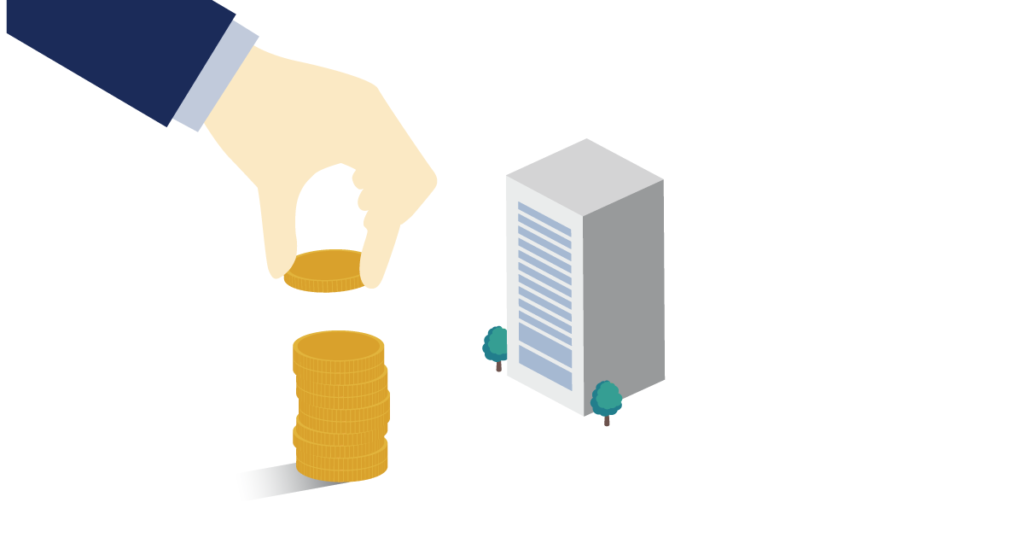
立ち退き料は、立ち退きを求める事情や借主の状況によって内容や水準が大きく変わります。一律の基準があるわけではなく、補償の考え方や交渉の進め方、物件の用途などによって異なります。
ここでは、立ち退き料に含まれる主な費目と、居住用・事業用それぞれにおける一般的な相場感をご紹介します。
立ち退き料を決める要素
立ち退き料の金額は、法律で一律に定められているものではなく、個別の事情によって大きく異なります。
借地借家法第28条では、立ち退き料は正当事由の有無を判断する際の一要素とされています。借主・貸主の事情や、建物の使用状況などを踏まえて、総合的に判断されることが通常です。正当事由の有無の判断においては、以下の点もあわせて評価されます。
- 貸主および借主(転借人を含む)が建物を必要とする事情
- 賃貸借契約に至る経緯
- 建物の利用状況
- 建物の現況
これらの要素がどちらにどれだけ有利に働いているかによって、立ち退き料の金額も変動します。たとえば、借主に居住実態があり、代替物件の確保が難しい場合は、立ち退き料が高額に設定される傾向にあります。一方で、建物の老朽化が進み、補修の緊急性が認められる場合などは、比較的低額になることが一般的です。
居住用物件の場合
立ち退き料の相場は、立ち退き前と同等の住環境を確保できるだけの金額が目安とされます。概ね賃料の6〜12か月分程度が一般的です。立ち退き料には主に以下の4つの項目が含まれます。
・引越し費用および新居の契約関連費用
移転先の仲介手数料・敷金・礼金のほか、引越し作業にかかる費用など。
・退去日までの賃料の免除
立ち退きにともなう負担軽減として、残存期間の賃料が免除されるケース。
・サービス解約にともなう費用
インターネット回線や電気・ガスなど、契約中のサービスを解約・変更するための費用とその手続き費用。
・慰謝料(精神的補償)
近隣との人間関係の喪失など、精神的苦痛に対する補償。いわゆる「迷惑料」としての意味合いもあり、慰謝料相当分を別途加算することもあります。
これらすべてを合計した金額で、概ね「賃料の6〜12か月分程度」に収まることが多いです。なお、立ち退き料には明確な計算式があるわけではなく、あくまでも目安となります。個別の事情や交渉状況によって金額は変動します。
事業用物件の場合
事業用物件の立ち退きは、居住用物件に比べて影響が大きいため立ち退き料が高額になりやすいです。
目安は賃料の1〜3年分程度とされています。しかし、事業用の立ち退き料は条件や規模、業種により大きく変動するため、画一的な相場はありません。そのため、販売拠点として実績を積み重ねてきたテナントの退去交渉は、居住用物件に比べて難航する傾向にあります。
事業用物件の立ち退き料には、以下の項目が含まれます。
・移転経費
引越し先の確保・契約金・引越し費用など、居住用と同様の基本的な移転費用です。
・借家権および造作物の評価額
土地家屋調査士による借家権の評価に基づき、借主の貢献により形成された利益部分が補償対象となります。加えて、店舗イメージや機能向上のために設置した造作物の買取費用も含まれます。
・営業補償
移転による休業、売上減少、設備の再整備など、営業への影響を金銭換算した補償です。電話番号の変更、名刺や封筒の作り直しなど、事業再開に向けた諸対応も対象になります。
このように多岐にわたることから、立ち退き交渉が1~2年ほどかかることもあります。なお、来客型のテナントほどではありませんが、事務所やオフィスも同様です。賃料の6か月分以上が目安となります。
事業用物件の場合、損失や補償額の予測が困難であり、貸主と借主の意見が対立するケースも少なくありません。特に、立地変更による売上への影響が大きいケースでは、補償の妥当性が争点になりがちです。
また、立ち退き後の収益や営業再開時期は不確定となるため、立ち退き料の金額は試算ベースでしか判断できません。こうした背景から、当事者間で合意が難しい場合には、裁判所の判断を仰ぎながら進めることもあります。
老朽化にともなう立ち退きの流れ

立ち退きには、法的な正当事由や補償内容とあわせて、借主との丁寧なやり取りが欠かせません。特に老朽化を理由とするケースでは、安全性や建て替えの必要性を誠実に説明しながら、円滑に合意形成を進めていく姿勢が求められます。
ここでは、老朽化を理由とした立ち退きにおいて、貸主が取るべき基本的な対応の流れを整理します。
①借主に立ち退きを申し出る
貸主の都合で立ち退きを求める場合には、契約満了の1年前から6か月前までに入居者へ通知する義務があります。
この通知は書面で行うことが原則です。ただし、立ち退きを円滑に進めるためにも、入居者への訪問や対面での説明といった丁寧な対応が重要です。
②立ち退きの理由や経緯を文書で通知する
まずは、建て替え予定があることを入居者に対して丁寧に通知します。これが入居者との最初の接点となるため、送付する文面には細心の注意が必要です。建物の老朽化により、安全性や機能面で不安が生じていることを丁寧に説明します。
さらに、建て替えの必要性についても、わかりやすく伝えることが重要です。そのうえで、任意での退去に協力してもらいたいという姿勢を、低姿勢かつ誠実に示しましょう。
この段階で入居者の心証を損ねてしまうと、その後の立ち退き交渉が難航する可能性があります。あくまでも協力をお願いするというスタンスを保ち、相手の立場に配慮したコミュニケーションを心がけましょう。
③入居者へ口頭で説明を行う
書面送付後は、入居者一人ひとりに個別に連絡し、丁寧に説明する時間を設けることが重要です。必ず事前にアポイントを取り、説明のための時間をもらえるよう、十分な配慮を心がけましょう。
入居者一括で対応した方が速いといった考え方もあるでしょう。しかし、普段面識のない入居者同士が、立ち退きという共通の課題をきっかけに結束するケースもあります。場合によっては、反対運動や立ち退き料の一斉吊り上げなどにつながりかねません。
立ち退き交渉は、できるだけ一対一で、個々の事情に寄り添いながら丁寧に進めていくことが望ましいでしょう。
④立ち退き料に関する交渉を行う
交渉のポイントは、立ち退き料をどの程度に設定するかという点です。多くの入居者は、納得できる立ち退き料が提示されれば、一定期間内での退去に応じる傾向があります。
一般的に納得のいく立ち退き料とは、引越しにかかる実費プラスアルファとなります。たとえば、同等の物件へ移転するための費用を、貸主側で負担するケースなどです。具体的には、敷金・礼金・仲介手数料・引越し費用などが含まれます。加えて一定の補償金を上乗せすることで、合意に至るということが少なくありません。
ただし、立ち退きを急ぐあまりに安易に高額な提示をすることは避けるべきです。引越し費用などについてはあくまでも実費ベースで考えましょう。
プラスアルファにあたる慰謝料や協力金などについては、個別の状況や入居者の事情に応じた判断が必要です。不安がある場合は、弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
⑤退去手続きを進める
立ち退きは通常の退去とは異なり、できるだけ早期の退去をお願いすることが一般的です。そのため、それに見合った配慮が必要となります。
たとえば、最終月の賃料や原状回復費用の免除、敷金の全額返還などです。柔軟に対応することで印象も良くなり、前向きに協力してもらえる可能性が高まります。
立ち退き交渉をスムーズに進めるための合意形成を円満に進めることが大切です。
賃貸管理業務におけるポイント
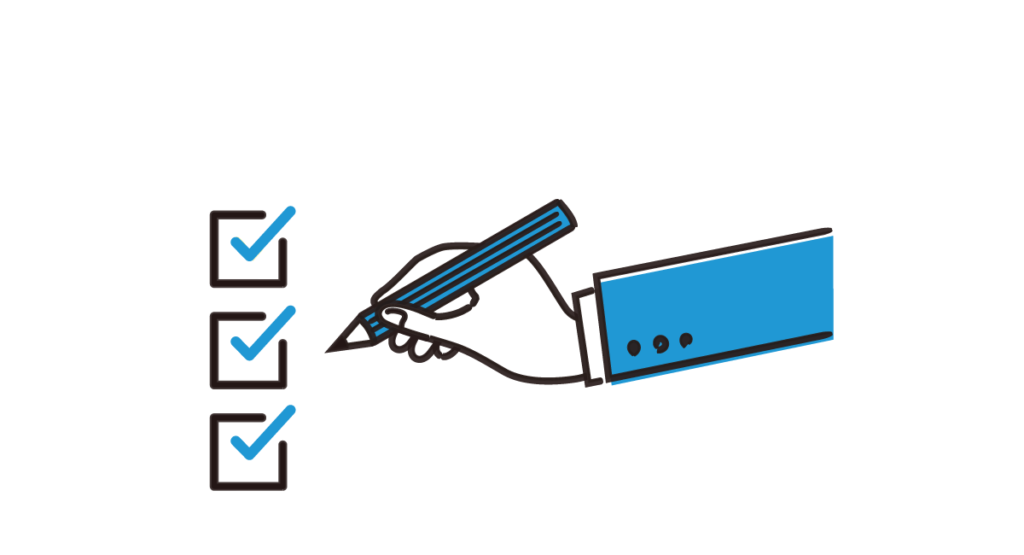
管理会社は立ち退き交渉において、円滑な補償交渉に加えて、入居者対応や管理体制のあり方が問われます。実際の交渉をスムーズに進めるためには、事前の準備や日常的な信頼構築、そして法的なリスクへの理解が欠かせません。
ここでは、賃貸管理業務において、立ち退き交渉を円滑に進めるためのポイントについて整理します。
入居者との信頼関係を日頃から築いておく
交渉をスムーズに進めるためには、入居者との日常的な信頼関係の構築が欠かせません。立ち退き料に関するやり取りは、基本的に交渉によって決まるものであり、信頼関係の有無が合意形成に大きく影響します。
たとえ建物の老朽化といった「正当事由」があったとしても、入居者にとっての立ち退きは大きなストレスとなるものです。不安や抵抗感を覚えるのも当然であり、マニュアル通りの対応ではフォローしきれないケースも少なくありません。
たとえば、点検予定や修繕の案内などをこまめに発信することで、物件の管理状況を入居者に正確に伝えることができるでしょう。また、老朽化に関する情報も定期的かつ段階的に共有しておけば、将来的な建て替えや退去の話にもつなげやすくなるはずです。
『いい生活Home』は、管理会社と入居者のコミュニケーションを円滑化するアプリです。点検予定の通知や老朽化に関する情報共有、質問への迅速な対応が可能です。日常的な接点を増やすことで、入居者の安心感や信頼感の向上を実現します。
非弁行為にならないようにする
非弁行為とは、弁護士の資格を持たない者が報酬を得る目的で法律業務を行うことを指します。立ち退き交渉において、報酬を受け取って代理交渉ができるのは、弁護士または認定司法書士に限られます。
不動産会社が立ち退き交渉を行う場合は、無償対応とすることで、非弁行為に該当しないと位置づけることが一般的です。しかし、立ち退き完了後に当該物件を売却した場合、仲介手数料が実質的な報酬と判断されるリスクもあります。
なお、無資格者が報酬を得て交渉を行った場合、弁護士法第77条第3号により、「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科される可能性があります。非弁行為の境界線を十分に理解したうえで対応することが欠かせません。
事前シミュレーションを徹底する
物件の取得や管理受託を行う前段階で、立ち退き料の試算を行い、想定されるコストを事前に把握しておくことも重要です。
賃貸人・賃借人双方の事情を具体的に比較したうえで、立ち退き料が賃料換算で数年分に相当する高額になるケースもあります。必要に応じて専門家の助言を受けつつ、立ち退き料を含む総コストを精査しておきましょう。
その際、立ち退き費用の目安や算出根拠を参考にすることが大切です。相手方にどの程度の負担が生じるかを慎重に見極めたうえで、適切な立ち退き料を設定することが求められます。
なお、賃借人に立ち退き料を提示する際は、明細書(計算書)を事前に準備しておくと、スムーズに交渉を進めやすくなります。提示金額の合理的な説明は、不信感の払拭にもつながります。
立ち退き料の相場を押さえて交渉を無理なく進めよう

立ち退き料に明確な計算式はありません。そのため、相場や内訳の基本を押さえておくことが重要です。特に、居住用・事業用物件それぞれの特性を理解したうえで、実費プラスアルファのバランスを意識すると良いでしょう。入居者が納得しやすい合理的な金額を提示することが、無理のない補償提案につながります。
また、交渉を円滑に進めるためには、入居者との信頼関係も重要になります。賃貸管理業務においては、『いい生活Home』のようなコミュニケーションツールの活用も一案です。点検予定の通知や老朽化に関する情報共有、質問への迅速な対応などを通じて、入居者の安心感を高めることができます。
立ち退きは、貸主・借主双方にとって負担の大きいテーマです。だからこそ、相場を冷静に見極めたうえで、誠実かつ段階的に進めていく姿勢が求められます。日頃からの関係づくりも意識し、無用なトラブルを未然に防ぎましょう。
・執筆者

株式会社いい生活 マーケティング本部
マーケティング部
広報部
全国の不動産市場向けイベント、セミナーなどにて多数登壇、皆様のお役に立つ最新情報を発信しております。


